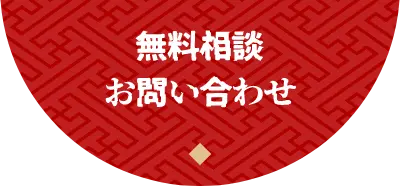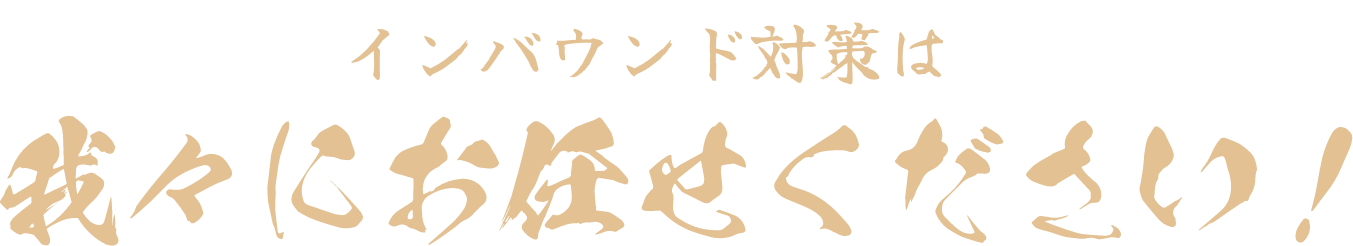低予算でインバウンド集客!マイクロインフルエンサーを活用した焼鳥店の成功事例
【目次】
低予算でインバウンド集客を狙うならマイクロインフルエンサーが最適
今や、集客にインフルエンサーを活用するのは珍しくなくなりました。どのようなインフルエンサーを起用するかはマーケティング企業の意向や予算規模によって変わるため、メガインフルエンサーを起用するケースもあれば、マクロインフルエンサーを起用するケースもあります。
起用すべきインフルエンサーの規模は変わるため一概には言えませんが、低予算で効率的にインバウンド集客を目指すなら、マイクロインフルエンサーの活用は有効な戦略のひとつです。
その理由は、主に以下の3点に集約されます。
費用対効果が高いから
マイクロインフルエンサーの最大の魅力は、圧倒的な費用対効果です。数千から数万人のフォロワーを持つ彼らは、メガインフルエンサーに比べてはるかに低コストでプロモーションを依頼できます。しかし、その影響力は侮れません。彼らのフォロワーは特定の分野に強い関心を持つ傾向があり、投稿に対する「いいね」やコメント、シェアといったエンゲージメント率が非常に高いのが特徴です。これは、単にフォロワー数が多いだけでなく、実際に店舗への来店や購買行動に繋がりやすいことを意味します。大型インフルエンサーへの依頼が数百万以上かかるのに対し、マイクロインフルエンサーは数万円、あるいは飲食の提供のみでプロモーションを引き受けてくれるケースもあり、限られた予算でも質の高いアプローチが可能です。
高い信頼性とリアルな情報発信が期待できるから
マイクロインフルエンサーの投稿は、高い信頼性を誇ります。彼らは自身のリアルな体験に基づいたレビューを発信するため、広告色が薄く、フォロワーは彼らの情報を友人の口コミのように信頼しやすい傾向にあります。特に、現地のリアルな情報を求める外国人観光客にとって、実際に店舗を訪れたインフルエンサーが発信する臨場感あふれる体験談は、ガイドブックや一般的な広告よりもはるかに強い訴求力を持つでしょう。彼らの投稿は、「行ってみたい」という感情を強く刺激し、実際の来店へと促します。
ピンポイントなターゲットアプローチができるから
マイクロインフルエンサーは、特定の趣味嗜好やライフスタイルを持つフォロワーを抱えていることが多いため、ターゲット層へのピンポイントなアプローチを可能にします。自店のコンセプトやターゲット顧客層に合致するインフルエンサーを選定することで、効率的に潜在顧客にリーチできます。例えば、日本の食文化に興味を持つ外国人や、特定の観光地巡りが好きな層など、より細かくターゲットを絞り込み、無駄なく情報を届けることが可能です。これは、不特定多数に広く浅く情報を発信する大型インフルエンサーでは難しい、効率的な集客を実現します。
これらの理由から、飲食店がインバウンド集客を成功させるためには、大型インフルエンサーの「数」よりも、マイクロインフルエンサーの「質」と「費用対効果」に注目し、戦略的に活用することが賢明な選択と言えるでしょう。
マイクロインフルエンサーを活用した焼鳥店Aの成功事例
ここからは、マイクロインフルエンサーを活用してインバウンド集客に成功した焼鳥店Aの成功事例を紹介します。
インバウンド集客への挑戦と立ちはだかる壁
宮城県仙台市にある焼鳥店Aは、地元の常連客に愛されるアットホームな雰囲気が魅力の老舗です。しかし、近年、少子高齢化と人口減少の波を受け、国内市場だけでは売上の維持が厳しくなってきました。そこで、新たな顧客層として着目したのが、コロナ禍を経て回復傾向にあるインバウンド観光客です。焼鳥店Aもこの流れに乗り、インバウンド需要を取り込むことで、経営の安定化とさらなる成長を目指していました。
しかし、焼鳥店Aは、インバウンド集客に取り組む上でいくつかの大きな課題に直面していました。
まず、最大の壁は「予算の制約」でした。中小規模の個人経営店である焼鳥店Aにとって、大手旅行代理店への委託や海外向けの広告出稿といった大規模なプロモーションは現実的ではありません。限られた予算の中で、いかに効果的に外国人観光客にアプローチするかが喫緊の課題でした。多言語対応のウェブサイト制作や翻訳ツールの導入にも、大きな費用がかかるため、そこにも十分な投資ができていませんでした。
次に、「情報発信力の不足」も深刻でした。焼鳥店Aは、これまで主に口コミや地域情報誌、そしてごく一般的なグルメサイトでの情報発信に留まっていました。外国人観光客が情報を収集する主要なチャネルであるSNS、特にInstagramやTikTokといったビジュアル重視のプラットフォームでの露出がほとんどなく、海外からの認知度は皆無に等しい状況でした。英語でのメニュー表記も不十分で、外国人観光客が安心して来店できるような環境が整っていませんでした。
さらに、「地理的・立地的な不利」も無視できませんでした。焼鳥店Aは仙台市の中心部からやや離れた場所に位置しており、観光客が自然と立ち寄るような人通りの多いエリアではありませんでした。そのため、意図的に店舗を探して来てもらうための「動機付け」が必要不可欠でした。単に「美味しい焼鳥店」というだけでは、数ある飲食店の中から選ばれる理由にはなりにくかったのです。
これらの課題を克服し、低予算で効果的なインバウンド集客を実現するために、焼鳥店Aは新たな戦略を模索する必要に迫られていました。そこで注目したのが、高い費用対効果と信頼性を兼ね備えたマイクロインフルエンサーの活用だったのです。
インバウンド集客における焼鳥店の強み
焼鳥店がインバウンド集客において持つ最大の強みは、そのユニークな食文化体験にあります。外国人観光客にとって焼鳥は、単なる食事ではなく、目の前で職人が丁寧に肉を串に刺し、炭火で香ばしく焼き上げるライブ感あふれるパフォーマンス自体がエンターテイメントとなります。この視覚と嗅覚を刺激する体験は、写真を撮りたくなる衝動をかき立て、SNSでの拡散に繋がりやすいという大きなメリットがあります。
また、焼鳥は牛肉や豚肉、野菜など、多様な食材を一口サイズで手軽に楽しめるため、日本の食材の豊かさを体験するのに最適です。部位ごとの味わいの違いや、タレと塩、様々な味付けを選べる点も、外国人にとっては新鮮な発見となります。
さらに、焼鳥店は一般的に比較的リーズナブルな価格帯で、日本の本格的な居酒屋文化を体験できる点も魅力です。高級店だけでなく、気軽に立ち寄れるカジュアルな雰囲気の店も多いため、予算を気にせず、現地の人々に混じって日本の夜の食文化を満喫したいというニーズに応えられます。
このように、焼鳥店は「体験型飲食」「多様な食材の提供」「手軽な価格帯」という点で、インバウンド顧客にとって非常に魅力的な選択肢となり得るのです。
マイクロインフルエンサー施策導入の経緯
仙台市の焼鳥店Aは、限られた予算と情報発信力の不足という大きな課題を抱えながら、インバウンド集客の可能性を探っていました。これまで試行錯誤してきたものの、大手広告や旅行会社への依存はコスト面で非現実的であり、地元の口コミに頼るだけでは外国人観光客へのリーチは絶望的でした。英語メニューの導入やSNSでの発信も始めたものの、単独での努力では埋もれてしまうのが現状でした。
そんな中、焼鳥店Aの店主は、オンラインでの情報収集を通じて、マイクロインフルエンサーの成功事例が世界中で増えていることに注目しました。特に、ニッチな分野で熱心なファンを持つ彼らが、費用を抑えつつも高いエンゲージメント率を叩き出しているという事実に惹かれたからです。一般的な広告とは異なり、個人のリアルな体験談として発信される情報は、フォロワーからの信頼が厚く、購買行動に直結しやすいという点も、店主の心を動かしました。
「これなら、うちのような小さな店でも、大きな費用をかけずに外国人観光客にアピールできるかもしれない」
そう考えた店主は、自店の強みである「本格的な炭火焼鳥の味」と「アットホームな雰囲気」を、どのように外国人目線で魅力的に伝えられるかを検討し始めました。そして、実際に日本を旅している外国人マイクロインフルエンサーにアプローチし、彼らに店舗を体験してもらい、その魅力を発信してもらうという具体的な戦略へと舵を切ったのです。
初期マイクロインフルエンサー施策の詳細
焼鳥店Aがインバウンド集客のために導入した初期のマイクロインフルエンサー施策は、限られた予算の中で最大限の効果を引き出すための、戦略的なアプローチでした。その中心にあったのは、「体験の提供とリアルな発信」、そして「ターゲットを絞った選定」です。
まず、焼鳥店Aは、日本への旅行に特化したSNSアカウントを持つ外国人マイクロインフルエンサーに狙いを定め、特に美食やローカル体験に関心が高いフォロワーを持つインフルエンサーを優先的にリストアップしました。
選定の際は、フォロワー数だけでなくエンゲージメント率(「いいね」やコメントの数)や投稿内容の一貫性、そして何よりも「日本の食文化を心から楽しんでいる」姿勢が見えるかを重視し、フォロワー数よりも焼鳥店Aの魅力と合致する層に響く発信力を持つ人物を選ぶことに注力しました。
アプローチは、SNSのダイレクトメッセージやメールを通じて丁寧に行いました。一般的なPR依頼とは異なり、仙台という地域の魅力や、焼鳥店Aが提供する「本物の日本の夜の食体験」を前面に押し出し、共感を呼び起こすことを意識しました。
インフルエンサーにとっても価値のある体験を提供するための提案を積極的に行った点も、特筆すべきポイントです。
報酬は現金ではなく、店舗での飲食を無償提供する「ギブアウェイ方式」を基本とし、交通費の一部補助や、市内の観光案内を提案するなど、インフルエンサーが来店しやすい環境を整えました。
来店時には、店主自らがインフルエンサーを温かく迎え入れ、焼鳥の調理過程や食材のこだわり、さらには仙台の食文化について丁寧に説明しました。単に料理を提供するだけでなく、「日本の食のストーリー」を伝えることに注力したのです。英語でのコミュニケーションが不慣れな部分もありましたが、翻訳アプリや簡単な英語を交えながら、心を込めておもてなしをしました。インフルエンサーが自由に撮影できるよう配慮し、質問には快く応じることで、彼らが質の高いコンテンツを制作できるような環境を提供しました。
投稿内容に関しては、店側から厳密な指示は行いませんでした。インフルエンサー自身の言葉で、感じたことや驚いたことを正直に発信してもらうことを重視しました。ただし、ハッシュタグには「#仙台」「#仙台グルメ」「#焼鳥」「#Sendai」「#YakitoriJapan」など、関連性の高いキーワードを複数含めるよう依頼し、検索からの流入を意識しました。また、投稿の際には、焼鳥店AのSNSアカウントをメンションしてもらうことで、相互のフォロワー流入を促進しました。
これらの初期施策は、低予算ながらも外国人観光客への認知度向上と「リアルで信頼性の高い情報」の拡散に大きく寄与し、焼鳥店Aの外国人観光客の来店数増加につながっています。
マイクロインフルエンサー施策がもたらした驚きの成果
焼鳥店Aが導入したマイクロインフルエンサー施策は、低予算ながらも予想をはるかに上回る集客効果と売上向上を実現しました。特にインバウンド顧客層へのアプローチにおいて、その成果は顕著でした。
- フォロワー数・投稿のリーチ数の飛躍的増加
施策前はわずかなSNSフォロワーしかいませんでしたが、マイクロインフルエンサーを活用したところ3ヶ月でInstagramフォロワーが約3倍に急増、特に外国人フォロワーが増加しました。インフルエンサー投稿は数万〜十数万リーチを記録し、調理風景や彩り豊かな串、楽しそうな表情の投稿は強いインパクトを与えました。「#SendaiFood」などのハッシュタグ戦略も奏功し、検索流入も大幅に増加しました。 - 来店客数と売上の明確な変化
SNSエンゲージメント向上後、新規顧客は1ヶ月で1.5倍に増加。特に外国人観光客が急増し、新規来店客の約3割を占めるまでになりました。また、週末には連日外国人客が見られるように。この来店客数増加に伴い、3ヶ月で月間売上は前年同期比20%増を達成。外国人観光客は高単価メニューを積極的に注文し、リピート来店も多く、売上と客単価向上に大きく貢献しました。 - 外国人観光客からのポジティブなフィードバック
来店した外国人観光客から多くの温かいフィードバックが寄せられました。彼らは「Instagramで見た通り」「写真以上に美味しい」「英語メニューがあり助かる」「日本の居酒屋文化を体験できた」と、SNSでの期待通りの体験に満足していました。目の前で焼く様子を楽しみ、動画をSNSに投稿する人も。「仙台で一番印象に残った焼鳥」といった声も聞かれ、これらの具体的な意見は施策の有効性と店舗スタッフのモチベーション向上に繋がっています。
飲食店のインバウンド集客におけるマイクロインフルエンサー活用時の費用相場
飲食店がインバウンド集客にマイクロインフルエンサーを活用する際の費用は、施策の内容やインフルエンサーのフォロワー数、エンゲージメント率によって変動しますが、比較的低予算で実施できるのが大きな魅力です。
基本的な費用相場
マイクロインフルエンサーの報酬は、「フォロワー数 × フォロワー単価」で計算されるのが一般的です。費用は業界・国・言語・フォロワー属性・媒体によって変動するため一概には言えませんが、フォロワー単価の相場は、1フォロワーあたり1円〜4円程度が目安とされています。
フォロワー1万人〜10万人規模のマイクロインフルエンサーなら、1投稿あたり1万円〜40万円程度になる計算です。
媒体によっても費用に差があり、主なSNSにおける費用相場は次のとおりです。
| Instagram リール動画 | 約5万円 |
| Instagram 画像・カルーセル投稿 | 約5万円 |
| Instagram ストーリーズ | 約3.5万円 |
| TikTok | 2万円〜7万円程度 |
Instagramのリール動画で約5万円、画像・カルーセル投稿で約5万円、ストーリーズで約3.5万円というデータもあります。
TikTokの場合は、2万円〜7万円程度が相場とされています。
この金額は、メガインフルエンサー(フォロワー100万人以上)が1投稿あたり300万円〜かかることを考えると、非常にリーズナブルと言えます。
報酬体系の種類
報酬の支払い方法には、主に以下のパターンがあります。
- 固定報酬型
最も一般的な形式で、上記の「フォロワー数 × フォロワー単価」で報酬を支払います。 - ギブアウェイ(無償提供)
現金報酬ではなく、店舗での飲食を無償で提供する形です。特に、飲食店においては、インフルエンサーが「食体験」を求めていることが多いため、この形式で協力してくれるケースも少なくありません。低予算で始めたい店舗にとって、非常に有効な選択肢です。 - 成果報酬型
投稿からの来店数や売上など、具体的な成果に応じて報酬を支払う形式です。ただし、成果の計測が難しい場合もあるため、事前にインフルエンサーと明確な合意形成が必要です。 - ハイブリッド型
固定報酬と成果報酬を組み合わせることもあります。
追加で発生する可能性のある費用
基本報酬以外に、以下のような費用が発生する場合があります。
- 交通費・宿泊費
遠方からインフルエンサーを招く場合、交通費や宿泊費の一部または全額を負担するケースがあります。 - 追加投稿費用
依頼した投稿数を超えるストーリーズやリール動画の追加投稿を依頼する場合、別途費用が発生することがあります。 - 二次利用費用
インフルエンサーが制作したコンテンツを、店舗のウェブサイトや他のSNS広告などで二次利用したい場合、別途費用が発生する可能性があります。契約時にその範囲を明確にしておくことが重要です。 - キャスティング会社利用料
インフルエンサーとのマッチングを専門業者に依頼する場合、別途手数料(インフルエンサー報酬の10〜30%程度)や月額費用が発生します。
費用を抑えるコツ
インフルエンサーに依頼する費用を抑えるには、次の工夫が有効です。
- ギブアウェイを基本とする
特に初期段階や予算が少ない場合は、無償提供を積極的に活用しましょう。 - インフルエンサーとの直接交渉する
キャスティング会社を挟まず、インフルエンサーと直接交渉することで、手数料を削減できます。 - 「体験価値」を提供する
単に食事だけでなく、特別な体験(例:料理教室、裏メニューの試食、店主との交流)を提供することで、インフルエンサーにとって魅力的な依頼となり、金銭的報酬以外の価値を感じてもらいやすくなります。
飲食店のマイクロインフルエンサー施策:SNS投稿の内容と演出のポイント
マイクロインフルエンサーを活用した飲食店の集客を成功させるには、SNS投稿の内容と演出に徹底的にこだわることが重要です。単なる「美味しい」の羅列ではなく、フォロワーの心を掴み、来店へと繋がるような魅力を引き出すポイントを以下に解説します。
1. ライブ感と体験の共有
投稿の核となるのは、「ここでしか味わえない体験」を伝えることです。単に料理の写真だけでなく、調理中の煙が立ち込める様子、焼鳥が炭火で焼ける音、店主が笑顔で接客する姿など、五感を刺激するライブ感を演出しましょう。インフルエンサーには、食事中の楽しそうな表情や、料理が運ばれてきた瞬間の驚きなど、リアルな感情が伝わる瞬間を捉えてもらうのが効果的です。例えば、目の前で寿司を握る職人の手元や、カクテルをシェイクするバーテンダーの動きなど、その店ならではの「ライブパフォーマンス」を強調することで、フォロワーはまるでその場にいるかのような感覚を味わい、強い興味を抱きます。
2. ストーリー性のある情報発信
料理の背景にあるストーリーを伝えることで、投稿に深みが増します。例えば、食材の産地やこだわり、創業からの歴史、店主の料理への情熱など、単なる商品紹介に終わらない「物語」を語ってもらいましょう。インフルエンサーが店主と会話する様子や、生産者の顔が見えるようなエピソードを盛り込むことで、フォロワーは単に美味しいだけでなく、「何を、誰が、どのように作っているのか」という背景に共感し、店への愛着を抱きやすくなります。
3. 五感を刺激するクリエイティブ
写真や動画は、フォロワーの五感を刺激することを意識して制作しましょう。
- 視覚
料理の色彩、盛り付けの美しさ、店内の雰囲気など、見た目の魅力を最大限に引き出す高品質な写真や動画が不可欠です。自然光を活用したり、料理が最も美味しそうに見える角度から撮影したりと工夫を凝らしましょう。 - 聴覚
動画では、焼鳥が焼ける「ジューッ」という音、出汁の香りが立つ「フワッ」という音、箸で料理を掴む「パチッ」という音など、食欲をそそるサウンドを取り入れることで、より没入感を高められます。 - 嗅覚・味覚
直接的に伝えることはできませんが、インフルエンサーの表現力で「香ばしい香り」「とろける食感」「旨味が凝縮された味わい」といった言葉を使い、フォロワーの想像力を掻き立てましょう。
4. 地域性とローカル体験の強調
もし焼鳥店Aのように地方にある場合、その地域ならではの魅力と絡めて発信することも有効です。その土地の地酒とのペアリングや旬の食材を使った限定メニュー、あるいは店舗周辺の観光スポットと合わせて紹介することで、「その地方都市を旅するなら、この焼鳥店は外せない」という体験価値を創出できます。単なる飲食店の紹介ではなく、旅のハイライトとして位置づけることで、より多くの外国人観光客の関心を惹きつけられます。
5. 行動を促す明確なコール・トゥ・アクション(CTA)と情報提供
投稿の最後には、フォロワーに具体的な行動を促す明確なCTAを含めましょう。「予約はこちらから」「場所はこちら」といった具体的な情報だけでなく、SNSアカウントのタグ付け、ハッシュタグの活用をインフルエンサーに依頼することで、情報を求める外国人観光客がスムーズに店舗に辿り着けるように導線を確保することが重要です。多言語での情報提供も忘れずに行いましょう。
マイクロインフルエンサー活用術:ハッシュタグと翻訳で集客を最大化
飲食店のインバウンド集客においてマイクロインフルエンサーを効果的に活用するには、ハッシュタグ戦略と翻訳対応が鍵となります。これらは外国人観光客が情報を「見つけやすく」「理解しやすい」ようにするための、費用対効果の高い施策です。
1. ハッシュタグ戦略:見つけやすさを追求する
ハッシュタグは、情報を必要としている外国人観光客にリーチするための重要なツールです。以下のポイントを押さえましょう。
- 多言語対応
英語は必須ですが、ターゲットとする国・地域の言語(例:中国語、韓国語、タイ語など)でのハッシュタグも併用することで、より多くの層にアプローチできます。 - 地域名+カテゴリ
「#仙台グルメ」「#MiyagiFoodie」のように、地域名と飲食店のカテゴリを組み合わせることで、具体的な検索ニーズに応えられます。 - 具体的なメニュー名
「#YakitoriSkewers」「#ToriKawa (鶏皮)」など、具体的なメニュー名をハッシュタグにすることで、興味を持つ層にピンポイントで届きます。 - 体験・感情表現
「#JapanTravel」「#FoodExperience」「#AuthenticJapaneseFood」など、体験や感情を表すハッシュタグは、共感を呼び、保存やシェアに繋がりやすくなります。 - 独自ハッシュタグの活用
店舗独自のハッシュタグ(例:#焼鳥Aの夜)を作り、インフルエンサーに活用してもらうことで、UGC(User Generated Content)を促進し、ブランド認知度を高められます。 - 検索ボリュームの考慮
主要なハッシュタグの検索ボリュームを事前に調査し、露出効果の高いものを選ぶことも重要です。
2. 翻訳対応:理解しやすさを高める
インフルエンサーの投稿内容はもちろん、店舗側からの情報発信も多言語に対応させることで、外国人観光客の不安を解消し、来店へのハードルを下げられます。理解しやすさを高めるには、次のことを心がけると良いでしょう。
- 投稿キャプションの多言語化
インフルエンサーには、母国語での投稿に加え、英語でのキャプションも併記してもらうよう依頼しましょう。主要な情報は、店舗のSNSアカウントでも多言語で投稿します。 - 店内表示・メニューの翻訳
入口の看板、メニュー、支払い方法の案内など、外国人観光客が目にする可能性のあるものはすべて、正確な英語表記を基本とし、主要なターゲット層の言語も併記できると理想的です。特にメニューは、食材や調理法が想像しやすいよう、写真付きで簡潔な説明を加えることが重要です。 - AI翻訳ツールの活用
店頭での簡単なコミュニケーションやSNSでのコメント返信には、翻訳アプリやAI翻訳ツールを積極的に活用しましょう。完璧な文法よりも、伝えたい気持ちと迅速な対応が信頼に繋がります。 - シンプルで分かりやすい表現
翻訳する際は、直訳ではなく、文化的背景を考慮した、シンプルで分かりやすい表現を心がけましょう。専門用語や日本語特有の言い回しは避け、外国人にも理解しやすい言葉を選ぶことが大切です。
店舗で最大限の魅力を引き出すマイクロインフルエンサー撮影サポート体制
マイクロインフルエンサーを活用した飲食店の集客効果を最大化するには、来店時の撮影サポート体制の構築が不可欠です。インフルエンサーが質の高いコンテンツを制作できるよう、店舗側が積極的に環境を整えることで、その魅力がフォロワーにダイレクトに伝わりやすくなります。
1. 撮影しやすい環境の整備
最も重要なのは、光の確保です。料理が最も美味しそうに見えるのは自然光の下なので、日中の来店であれば窓際など明るい席を優先的に案内しましょう。夜間であれば、照明の明るさや色温度を調整し、料理が映える温かみのある光を演出できると理想的です。また、テーブル上のスペースを十分に確保し、インフルエンサーが機材を広げやすく、様々なアングルから撮影できるような配慮も大切です。
2. 撮影への理解と協力体制
店員全員がマイクロインフルエンサーの撮影に対する理解を持ち、協力的な姿勢で臨むことが重要です。インフルエンサーが撮影のために少し待たせたり、料理の配置を調整したりする場面があっても、快く対応するよう教育しておきましょう。写真や動画に店員が映り込む可能性がある場合は、事前に許可を取っておくなどの配慮も必要です。
3. 撮影スポットの提案と情報提供
店側から、おすすめの撮影スポットやアングルを提案することも有効です。例えば、「この席からだと○○が背景に見えますよ」「この焼鳥は盛り付けが特徴的なので、ぜひアップで撮ってみてください」といった具体的なアドバイスは、インフルエンサーの創作意欲を刺激します。また、料理のこだわりや、店内の歴史的な装飾など、写真映えする「ストーリー性のある情報」を積極的に提供することで、投稿の質を高めることができます。
4. プライバシーへの配慮と確認
他の来店客のプライバシーへの配慮も忘れてはなりません。撮影時に他のお客様が映り込まないよう席を調整したり、必要であれば声かけをしたりするなど、細やかな気配りが信頼関係を築きます。また、インフルエンサーが撮影したコンテンツを店側が二次利用したい場合は、事前に明確な許可を得ておくことがトラブル防止に繋がります。
他店舗にも応用できる!マイクロインフルエンサー施策の実践ヒント
焼鳥店Aの成功は、他の中小規模飲食店にも応用できる実践的なヒントを多く含んでいます。特に低予算でインバウンド集客を目指すなら、以下のポイントを参考にマイクロインフルエンサー施策を導入してみましょう。
マイクロインフルエンサーの探し方
マイクロインフルエンサーを探す際は、単にフォロワー数を見るのではなく、「自店のターゲット層とマッチするか」「エンゲージメントが高いか」を重視しましょう。
- SNSでのキーワード検索
InstagramやTikTokで、「#JapanTravel」「#TokyoFoodie」「#OsakaCafe」「#[地域名]グルメ」「#日本旅行」といったハッシュタグを検索します。投稿内容が自店のコンセプトと合致し、写真や動画のクオリティが高いアカウントを探しましょう。 - 旅行関連アカウントからの派生
日本専門の旅行情報アカウントや、特定の都市を紹介するアカウントが過去にタグ付けしていたインフルエンサーをチェックするのも有効です。 - エンゲージメント率の確認
フォロワー数に対して「いいね」やコメント、シェアの数がどれくらいあるかを確認しましょう。エンゲージメント率が高いアカウントほど、フォロワーへの影響力が期待できます。 - DMでの丁寧なアプローチ
興味を持ったインフルエンサーには、SNSのダイレクトメッセージやメールで直接連絡を取ります。その際、定型文ではなく、相手の投稿内容に触れながら「なぜあなたに依頼したいのか」「どのような体験を提供したいのか」を具体的に伝え、共感を促すことが重要です。
少額から始める予算設計のコツ
低予算でも効果を出すためには、費用対効果を最大化する工夫が必要です。費用対効果を最大化するには次のことを検討しましょう。
- ギブアウェイ(無償提供)を活用する
現金での報酬ではなく、店舗での飲食を無償提供する「ギブアウェイ方式」を基本としましょう。インフルエンサーにとっても、美味しい食事を体験できることは大きな魅力です。 - 交通費の一部補助を検討する
遠方からのインフルエンサーには、交通費の一部を補助することで、来店へのハードルを下げられます。全額ではなく、一部負担でも十分な動機付けになります。 - 「体験」の価値を最大化する
単なる食事だけでなく、調理体験、店主との交流、地元の文化紹介など、インフルエンサーにとって特別な「体験価値」を提供することで、現金報酬以上の魅力を感じてもらえます。 - 成果報酬型も視野に入れる
初回はギブアウェイとし、その後の成果(例:SNSからの来店数)に応じて、次回のプロモーションや追加報酬を検討するなど、成果報酬型の要素を取り入れることも有効です。 - 地道な関係構築を心がける
一度で終わらせず、良好な関係を築くことで、今後の継続的な協力や、別のインフルエンサーの紹介にも繋がる可能性があります。
これらのヒントを参考に、あなたの店舗でもマイクロインフルエンサーを活用した集客施策にぜひ挑戦してみてください。
マイクロインフルエンサー施策:投稿依頼時の注意点とNG例
マイクロインフルエンサーに投稿を依頼する際、効果を最大化し、トラブルを避けるためには、いくつかの重要な注意点があります。特に避けるべきNG例を理解することで、双方にとって有益な協力関係を築けます。
良好な関係構築と効果最大化を助ける依頼時の注意点
マイクロインフルエンサーに依頼をする際は、次のことに注意して依頼しましょう。
- 明確な期待値を共有する
- 依頼内容の具体化
どのような投稿(写真、動画、ストーリーズ、リールなど)、投稿数、使用してほしいハッシュタグ、メンションすべきアカウントなどを明確に伝えます。 - 期日の設定
投稿の希望日時や最終期日を具体的に伝えましょう。ただし、インフルエンサーのスケジュールも考慮し、柔軟性を持たせることも大切です。 - 成果物利用の許諾
投稿された写真や動画を、店舗のSNSやウェブサイトで二次利用したい場合は、事前に明確な許諾を得ておきましょう。これにより、後々のトラブルを防ぎ、店舗側の情報発信にも役立てられます。
- 依頼内容の具体化
- インフルエンサーの自由度を尊重する
- クリエイティブな裁量
細かすぎる指示はインフルエンサーの創造性を阻害し、不自然な投稿になりがちです。基本的な方向性や伝えたいポイントは共有しつつ、具体的な表現方法は彼らのセンスに任せましょう。リアルな投稿こそ、フォロワーの共感を呼びます。 - 本音での発信を推奨
店舗にとって都合の良いことばかりを言わせるのではなく、彼らが実際に感じた魅力を正直に表現してもらうよう促します。良い点だけでなく、もし改善点があればそれも受け入れる姿勢が、信頼性のあるコンテンツに繋がります。
- クリエイティブな裁量
- 丁寧なコミュニケーションを心がける
- 感謝の気持ち
依頼時だけでなく、来店時、投稿後にも感謝の気持ちを丁寧に伝えましょう。良好な人間関係が、今後の継続的な協力関係の基盤となります。 - 迅速な対応
質問や疑問点があった際には、迅速に返信することを心がけましょう。スムーズなコミュニケーションは、インフルエンサーのモチベーション維持にも繋がります。
- 感謝の気持ち
- 法令遵守と透明性
- PR表記の徹底
依頼された投稿であることを示す「#PR」や「#Ad」などの表記を必ず含めてもらいましょう。これは景品表示法などの法令遵守の観点から非常に重要であり、フォロワーからの信頼を得るためにも不可欠です。
- PR表記の徹底
信頼を損なう避けるべきNG行為
次の行為は、インフルエンサーの信頼を損ないます。くれぐれも行わないようにしましょう。
- 過度な成果要求やプレッシャー
「〇〇人集客できるまで投稿してほしい」「売上が上がらないのはあなたのせいだ」といった、無責任な成果要求や過度なプレッシャーをかけるのは絶対に避けましょう。これはインフルエンサーのモチベーションを著しく低下させ、関係悪化の原因となります。 - 投稿内容への過度な干渉・修正指示
「この表現は気に入らないから修正しろ」「もっと商品を褒めろ」といった、一方的な修正指示や感情的な要求はNGです。インフルエンサー自身の言葉でなければ、フォロワーには不自然に映ります。意見を伝える際は、具体的な理由を添え、あくまで提案の形で行いましょう。 - 無償での過剰な要求
飲食提供のみにも関わらず、複数回の投稿や友人の招待、他のインフルエンサーの紹介まで求めるなど、提供する価値に見合わない過剰な要求は避けましょう。ギブアウェイはあくまで「協力」であり「搾取」ではありません。 - 連絡不精・音信不通
依頼後、インフルエンサーからの質問に全く返信しない、投稿後に感謝の連絡をしないなど、コミュニケーションを疎かにするのは信頼関係を壊します。 - 法令遵守を無視した依頼
PR表記をしないよう指示したり、事実と異なる誇大な表現を要求したりする行為は、法的な問題に発展するだけでなく、ブランドイメージを著しく損ないます。
マイクロインフルエンサーが拓く飲食店のインバウンド戦略と地域活性化
訪日外国人観光客の増加に伴い、飲食店のインバウンド集客ではマイクロインフルエンサー活用が注目されています。マイクロインフルエンサーの活用は低コストで費用対効果が高く、フォロワーからの信頼性も高いためリアルな口コミとして拡散しやすいのが特徴です。
今後は、ヴィーガンやアニメファンなどターゲットを細分化し、特定の分野に特化したマイクロインフルエンサーと連携を強化しましょう。彼らの視点に寄り添った情報発信は、深いエンゲージメントと実際の来店に繋がります。
マイクロインフルエンサーは、飲食店の集客だけでなく、地域の隠れた魅力を発掘・発信する「新しい地域案内人」としても活躍します。
今後は、インフルエンサーを活用したSNS発信と来店体験の一貫性を高め、地域行政との連携も視野に入れることが、持続的な成長の鍵となるでしょう。