
【目次】
インバウンド集客において国別戦略が重要な理由は、各国・地域の文化、習慣、価値観、情報収集方法、旅行目的が大きく異なるためです。
例えば、欧米圏の旅行者は長期滞在で多岐にわたる体験を重視する傾向がある一方、アジア圏の旅行者は短期間で効率的に多くの観光地を巡り、ショッピングを楽しむ傾向があります。また、宗教的な配慮や食文化の違いも無視できません。
これらの違いを無視し、一律のプロモーションを行うと、ターゲットに響かないだけでなく、誤解や不快感を与えかねません。各国・地域の特性を深く理解し、それに合わせた情報発信、商品・サービス開発、受入体制の整備を行うことで、より効果的に潜在顧客にアプローチし、満足度の高い旅行体験を提供できます。それは結果として、リピーター獲得や口コミによる拡散にも繋がり、持続的なインバウンド集客に貢献するでしょう。
本記事では、国と地域別にそれぞれの訪日客の特徴と効果的なアプローチ方法を解説します。
アメリカ人観光客は、長期滞在で多様な体験を重視し、レビューサイトを参考に個人旅行を楽しむ傾向があります。効果的なアプローチには、SNSでの体験型コンテンツ発信、地方の魅力紹介、そして英語対応とレビューサイトの高評価維持が鍵となります。
アメリカ人観光客は、一般的に長期滞在で多岐にわたる体験を重視する傾向があります。近年では、画一的な観光地巡りよりも、地域の文化体験、自然探索、アドベンチャースポーツ、グルメ、温泉、アニメ・漫画などのポップカルチャーへの関心が高まっています。特に、都会の喧騒から離れた地方でのユニークな体験や、日本の伝統文化を深く学べる機会を求める声が増えています。個人旅行や家族旅行が多く、質の高いサービスと快適性を重視する傾向も見られます。
効果的なプロモーションには、彼らが日常的に利用するプラットフォームの活用が不可欠です。Instagram、Facebook、TikTokなどのSNSでは、美しい写真や動画で日本の魅力を視覚的に訴求し、具体的な体験イメージを喚起することが重要です。特に、日本の伝統文化体験(茶道、着物、武道など)や、自然アクティビティ(ハイキング、サイクリング、スキーなど)といった体験型観光を前面に出したコンテンツは高い関心を集めます。インフルエンサーマーケティングも有効で、アメリカ人インフルエンサーに日本の魅力を発信してもらうことで、信頼性と訴求力を高めることができます。また、旅行系ブログやオンライン旅行メディアへの掲載も効果的です。
アメリカ人観光客にとって、スムーズな英語対応は必須です。観光案内所、宿泊施設、飲食店、交通機関など、あらゆる場面での英語表記や英語でのコミュニケーションが求められます。特に、QRコード決済やキャッシュレス決済への対応も重要です。また、旅行の計画段階でTripAdvisor、Yelp、Googleマップなどのレビューサイトを徹底的に活用する傾向があるため、これらのサイトでの高評価獲得は極めて重要です。利用客にレビュー投稿を促す仕組みを導入し、寄せられたレビューには迅速かつ丁寧に返信するなど、積極的な管理を行うことで、信頼性を高め、新規顧客獲得に繋げることができます。ポジティブなレビューは強力な集客ツールとなります。
中国人観光客は、爆買いから体験重視の個人旅行へシフト。効果的な戦略は、WeChatやREDなど中国SNSでの情報発信、KOL活用、Alipay/WeChat Payなどモバイル決済の整備です。ビザ取得の円滑化も重要となります。
近年の中国人旅行者は、以前のような爆買いに代表される大量消費から、体験重視、質の高いサービス、パーソナライズされた旅行へと消費傾向が変化しています。団体旅行よりも個人旅行(FIT)や小規模なグループ旅行が増加し、地方の隠れた名所や文化体験、美食、温泉、アニメ聖地巡礼など、よりディープな日本体験を求める層が増えています。また、健康志向や美容への関心も高く、日本の医療ツーリズムや美容関連サービスへの需要も高まっています。価格だけでなく、ストーリー性や希少価値、SNS映えする要素が購買意欲を刺激する重要な要素となっています。
中国人旅行者へのアプローチには、中国独自のSNSプラットフォームの活用が不可欠です。特に、WeChat(微信)は日常的なコミュニケーションツールであり、ミニプログラムを活用した予約・決済システム、情報発信、クーポン配布など、多角的な活用が可能です。RED(小紅書)は、旅行情報や商品レビューを共有するコミュニティ型SNSであり、ユーザー生成コンテンツ(UGC)が非常に重視されます。日本人事業者による公式アカウント開設に加え、中国人KOL(キーオピニオンリーダー)やKOC(キーオピニオンコンシューマー)との連携を通じて、リアルで信頼性の高い情報を発信し、口コミを喚起することが効果的です。視覚的に魅力的な写真や動画、体験談を豊富に掲載し、ライブコマースなども積極的に活用することで、購買意欲を高めることができます。
中国人観光客の誘致においては、ビザ取得の円滑化が依然として重要な要素です。ビザ緩和の動きは歓迎される一方で、申請プロセスの簡素化や多角的ビザの発給など、さらなる改善が期待されます。また、中国ではキャッシュレス決済が社会インフラとして広く普及しているため、日本国内でのAlipay(支付宝)やWeChat Pay(微信支付)といった主要なモバイル決済サービスの導入は、集客を大きく左右します。これら決済方法への対応は、中国人観光客の利便性を飛躍的に向上させ、消費を促進する上で不可欠です。多言語対応の充実(特に中国語簡体字)や、Wi-Fi環境の整備も、快適な旅行体験を提供し、リピートに繋がる重要な要素となります。
台湾人観光客はリピーター率が高く、インスタ映えやグルメ体験を重視します。戦略としては、繁体字での情報提供、現地メディア・KOL連携が不可欠。地方の隠れた魅力や季節限定コンテンツで、再訪意欲を高めることが重要です。
台湾人観光客は、世界的に見ても日本のリピーター率が非常に高いのが特徴です。この特性を活かすには、「何度来ても楽しめる日本」をアピールすることが重要です。具体的には、定番観光地だけでなく、地方の知られざる魅力、季節限定のイベント、特定のテーマ(例:鉄道、温泉、アート)に特化したツアー、日本独自の文化体験(例:伝統工芸、農業体験)などを積極的に提案することが有効です。また、リピーター向けの割引や特典、会員プログラムを設けることも、再訪を促す強力なインセンティブになります。過去の訪問歴に基づいたパーソナライズされた情報提供も、顧客ロイヤルティを高める上で効果的です。
台湾人観光客は、SNSでの情報共有が非常に活発であり、特にInstagramでの「インスタ映え」するスポットや体験を重視する傾向があります。美しい景色、ユニークなアート作品、可愛らしいカフェ、季節の花々など、写真映えするコンテンツを前面に出すことが重要です。また、日本のグルメに対する関心も非常に高く、ラーメン、寿司、和食はもちろんのこと、地方のB級グルメ、老舗の味、旬の食材を活かした料理など、多岐にわたる食体験が人気です。地元の食材を使った料理教室や、酒蔵見学と試飲など、食に関する体験型コンテンツは特に響きやすいでしょう。訪問者がSNSで積極的に発信したくなるような、視覚的・味覚的に魅力的な情報提供が求められます。
台湾では中国大陸で使われる簡体字ではなく、繁体字が公用語であるため、情報発信は必ず繁体字で行う必要があります。ウェブサイト、パンフレット、メニュー、表示など、あらゆる媒体で繁体字対応は必須です。加えて、台湾独自のメディア戦略も重要です。台湾の主要な旅行情報サイト、人気ブロガー、YouTuber、テレビ番組など、現地メディアとの連携を通じて、信頼性の高い情報を広く拡散することが効果的です。特に、人気KOL(キーオピニオンリーダー)による体験レポートや動画は、多くのフォロワーにリーチし、具体的な旅行計画のきっかけとなる可能性が高いです。現地の旅行会社との連携を強化し、台湾市場のニーズに合わせたツアー商品を共同開発することも有効な戦略となります。
韓国人観光客は短期・低予算旅行が多く、SNSの影響力が絶大です。アプローチには、KOL(インフルエンサー)活用による情報拡散、徹底した韓国語対応が不可欠。リピーター向けに地方の魅力や体験型コンテンツを提案し、再訪を促しましょう。
韓国人観光客は、地理的な近さから週末を利用した短期旅行や、LCC(格安航空会社)を利用した低予算旅行が多い傾向にあります。この特性を活かすには、短期間でも充実感を得られるような工夫が必要です。例えば、「弾丸グルメ旅」「週末温泉旅」「都心からアクセスしやすい自然体験」など、テーマを絞ったコンパクトなプランを提案することが有効です。また、費用を抑えつつも満足度を高めるために、無料または安価で楽しめる施設やイベントの情報提供、公共交通機関を効率的に利用できるモデルコースの提示などが喜ばれます。クーポンや割引情報の提供も、低予算旅行者にとっては大きな魅力となります。
韓国ではSNSの影響力が非常に強く、特にInstagramやYouTubeなどのKOL(インフルエンサー)が発信する情報は、旅行先の意思決定に大きな影響を与えます。日本の魅力的なスポットや体験を、韓国人KOLに実際に体験してもらい、そのリアルな感想や映像をSNSで発信してもらうことは、高い訴求力と信頼性を生み出します。また、ウェブサイト、パンフレット、施設内の案内表示、メニューなど、あらゆる情報における韓国語対応は必須です。特に、緊急時やトラブル発生時に円滑なコミュニケーションが取れるよう、多言語対応可能なスタッフの配置や翻訳アプリの導入なども検討すべきです。細かい部分まで韓国語で対応することで、安心感と親近感を与え、満足度向上に繋がります。
韓国人観光客はリピーター率も高く、特に若い世代は複数回日本を訪れる傾向にあります。リピーター対策としては、定番の観光地だけでなく、まだあまり知られていない地方の魅力や、季節限定のイベント、特定の趣味に特化した体験などを積極的に提案することが有効です。例えば、地域の祭り、伝統工芸体験、特定のテーマ(例:日本の鉄道、アニメの聖地巡礼)に沿った旅行プランなどが考えられます。また、航空路線が充実している主要都市だけでなく、地方への直行便誘致や、地方の公共交通機関でのアクセス改善情報の発信も、地方誘致には欠かせません。地方独自の魅力を前面に出し、多様なニーズに応えることで、さらなるリピーター獲得と観光客の分散化に貢献します。
インバウンド集客において、国・地域ごとの特性を理解し、適切なKPI(重要業績評価指標)を設定し、その効果を測定することは、戦略の成功に不可欠です。画一的な指標では真の成果を見誤る可能性があります。以下に、アメリカ、中国、台湾、韓国それぞれの国・地域におけるKPI設定と効果測定のポイントを解説します。
まず、共通して重要なKPIとしては以下のものが挙げられます。
これらの共通指標に加え、各国・地域の特性に応じた独自のKPIを設定し、測定することが重要です。
アメリカ人観光客は、長期滞在で多様な体験を重視し、個人旅行が多い傾向があります。
中国人観光客は、SNSの影響力が非常に強く、モバイル決済が主流です。
台湾人観光客はリピーターが多く、インスタ映えやグルメへの関心が高い傾向があります。
韓国人観光客は短期・低予算旅行が多く、SNSの影響力が大きいのが特徴です。
ここからは、ターゲット別のアプローチによってインバウンド集客する際のモデルケースを紹介します。
東京・浅草にある土産物店Aは、単なる物販だけでなく、店内で「甲冑試着体験」を提供。アメリカ人観光客の「日本の文化体験」への関心の高さに着目し、英語での案内を徹底しました。体験の様子をSNSで積極的に発信してもらうことで、UGC(ユーザー生成コンテンツ)が増加。TripAdvisorなどのレビューサイトでも高評価を獲得し、「日本でしかできないユニークな体験」として人気を博しました。結果、体験利用者の多くが土産物を購入し、客単価も向上。来店者数も前年比20%増を達成しました。
大阪・道頓堀のドラッグストアBは、中国人観光客の消費傾向の変化に対応するため、WeChat公式アカウントを開設し、人気KOL(キーオピニオンリーダー)と連携したライブコマースを実施。新商品や限定品をリアルタイムで紹介しました。また、店内ではAlipayとWeChat Payの利用を徹底し、スムーズな決済環境を整備。多言語対応可能なスタッフを常駐させ、購入体験の利便性を高めました。これにより、SNSからの来店誘導が成功し、モバイル決済による購入額が大幅に増加。売上全体の中国人比率が30%から50%に上昇しました。
東京・新宿のカフェCは、台湾人観光客の「インスタ映え」と「グルメ」への高い関心に着目し、季節ごとの限定スイーツや、店内のフォトジェニックな装飾を強化しました。繁体字でのメニュー表記や、撮影スポットの案内を設置。さらに、周辺の台湾人観光客に人気のスポット(アニメ聖地など)と連携したクーポン配布や情報発信を行い、周遊を促しました。結果、台湾人観光客のSNSでの投稿数が飛躍的に増加し、それが新たな来店客を呼び込む好循環を生み出しました。特に週末の台湾人客数が2倍に増加しました。
大阪・心斎橋にあるファッションビルDは、韓国人観光客の短期・低予算旅行の傾向と、K-POP文化への親近感に着目しました。LCC利用客向けの「週末限定お買い物クーポン」を配布し、短時間でもお得に楽しめる工夫を凝らしました。また、韓流アイドルが日本で撮影したMVのロケ地情報や、日本の若者文化発信地としての魅力を韓国語でSNS発信。特に、韓国の人気ファッションインフルエンサーとのコラボイベントを定期的に開催し、来店を促しました。これにより、特に20代の韓国人客層の来店が増え、SNS経由の売上が35%増加しました。
最後に今後のインバウンド市場のトレンド予測を解説します。次に挙げるトレンドは相互に関連し合いながら、今後のインバウンド市場を形成していくと考えられます。柔軟な対応と戦略的な取り組みが、持続的なインバウンド集客に繋がるでしょう。
今後のインバウンド市場において、「持続可能性(サステナビリティ)」と「エシカル消費(倫理的消費)」は避けて通れない重要なトレンドとなるでしょう。環境への配慮、地域経済への貢献、文化の尊重といった観点から、旅行先や旅行内容を選ぶ消費者が増加します。オーバーツーリズム問題への意識も高まるため、観光地側は環境負荷の低い観光プログラムの開発や、地域住民との共存を意識した受け入れ体制の構築が求められます。例えば、廃校を活用した宿泊施設での地域食材提供や、伝統工芸体験を通じた文化継承への貢献といった、ストーリー性のある旅行体験がより評価されるようになります。
AIやビッグデータ解析の進化により、観光客一人ひとりの嗜好や過去の行動履歴に基づいた「パーソナライゼーション」がさらに進展します。旅マエのプランニング段階から、AIチャットボットによる個別最適化された旅行プランの提案、現地のAI翻訳機能付きガイド、VR/AR技術を活用した没入型体験など、テクノロジーは旅行体験のあらゆるフェーズで活用されるでしょう。これにより、情報収集の効率化、言語の壁の解消、そして個々のニーズに合わせた唯一無二の旅行体験が提供可能になります。旅先での決済手段も、モバイル決済や生体認証など、よりシームレスで非接触型のものが主流となります。
従来の「ゴールデンルート」に代表される主要都市巡りだけでなく、旅行目的はさらに多様化します。ウェルネス・ツーリズム(健康志向の旅行)、アドベンチャー・ツーリズム、教育旅行、ワーケーションなど、特定のテーマに特化した需要が顕著になります。これに伴い、これまで観光客があまり訪れなかった地方への誘客が本格化します。地方には、その土地ならではの自然、文化、食、人との交流といった独自の魅力があり、これらを前面に押し出すことで、新たな価値を求める旅行者を惹きつけることができます。地方創生の観点からも、地域住民が主体となった観光コンテンツ開発や、地域資源を活かした体験型プログラムの提供が鍵となります。
世界的な情勢不安や感染症の経験から、旅行における「安全・安心」への意識は今後も高く維持されます。衛生管理の徹底、緊急時の情報提供体制、医療連携の強化などは、旅行先を選ぶ上で重要な要素となります。また、万が一のリスクに備えた旅行保険への加入促進や、旅行者への適切なリスク情報提供も求められます。観光地側は、非常時の対応計画を明確にし、多言語での情報発信体制を整えることで、旅行者の不安を軽減し、信頼感を醸成することが不可欠です。
インバウンド集客を最大化するには、画一的なアプローチではなく、国・地域ごとの特性に合わせた戦略が不可欠です。アメリカ人観光客には体験型コンテンツや地方の魅力を、中国人観光客にはSNSでの情報発信やモバイル決済対応を強化するなど、ニーズの深い理解に基づいた施策が「刺さる」集客に繋がります。繁体字対応や現地のKOL(インフルエンサー)活用、リピーター対策など、それぞれの市場に最適化したプロモーションと受け入れ体制を整えることで、顧客満足度を高め、持続的な集客と消費拡大を実現しましょう。
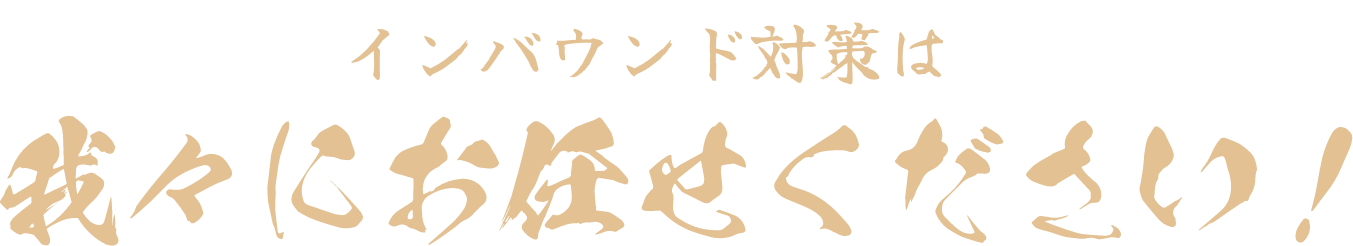
私たち、インバウンドマーケティングジャパンは、
訪日外国人観光客の集客支援に”とんでもなく”特化。
多言語対応のMEOやGoogle広告を活用したデジタルマーケティングの知見を生かし、訪日客の集客や来店促進、海外向けSNSの構築・運用、店舗のインバウンド対応まで、総合的な支援サービスを行っています。
「対策を進めたいが、どこから手をつけていいか分からない」とお困りですか?当社では、企業や店舗様の課題と目標に合わせた最適なプランをご提案いたします。無料での相談も受け付けていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください!