
【目次】
2025年のインバウンド市場は、2024年までの急速な回復期を経て、新たな局面を迎えると予想されます。世界的な旅行者動向と日本の独自の魅力、そして喫緊の課題を包括的に捉えることで、より持続可能な成長への道筋が見えてきます。
2020年以降のコロナ禍により壊滅的な打撃を受けた世界のインバウンド市場は、2023年から2024年にかけて目覚ましい回復を遂げました。国際連合世界観光機関(UNWTO)の報告によれば、2023年の世界の国際観光客到着数はパンデミック前の88%まで回復し、特に欧州や中東が牽引しました。日本においても、水際対策の緩和と円安を追い風に、2024年には訪日客数がコロナ禍前の水準を上回る月も現れるなど、急速な回復基調が鮮明になりました。特にアジア圏からの観光客が回復を牽引し、地方への誘客も徐々に進みつつあります。しかし、回復の度合いは国・地域によって異なり、航空便の回復状況や経済情勢などが影響を与えています。
2025年に向けて、世界の旅行者動向はいくつかの重要なトレンドを示しています。まず、「体験型消費」への志向がより一層強まるでしょう。単なる観光名所の訪問に留まらず、現地の文化や日常生活に触れることができる「コト消費」や「学びの旅」への需要もますます高まることが予想されます。
次に、「持続可能性(サステナビリティ)」への意識の高まりです。環境への配慮や地域社会への貢献を重視する旅行者が増え、エシカルツーリズムやエコツーリズムへの関心が高まってきています。
「パーソナライゼーション」の重要性も増しており、画一的なツアーではなく、個人の興味やニーズに合わせたカスタマイズされた旅行プランが人気です。
デジタル技術の活用も不可欠で、旅行計画から予約、現地での情報収集、決済に至るまで、スマートフォンを活用したシームレスな体験が求められます。
日本が世界から注目される理由は多岐にわたります。まず、豊かな文化遺産(京都の寺社仏閣、伝統的な祭りなど)と多様な自然景観(富士山、沖縄のビーチ、北海道の雪景色など)は、旅行者を惹きつける強力な磁力です。また、質の高いサービスと高い治安レベルは、安心して旅行できる国としての評価を確立しています。食文化も非常に魅力的で、和食はユネスコ無形文化遺産に登録されるなど、世界中でその人気が高まっています。アニメや漫画、J-POPなどのポップカルチャーも、若年層を中心に強力なインバウンドコンテンツとなっています。そして、現在の円安は、訪日外国人にとって購買力を高める要因となり、旅行費用を抑えられるという経済的なメリットを提供しています。
しかし、2025年以降の持続的な成長のためには、いくつかの課題も浮上しています。主な課題は次のとおりです。
日本のインバウンド市場がこれからも成長を続けるためには、これらの課題を解消することはもちろん、長期的な視点での観光戦略が求められます。
2025年のインバウンド市場は、各国の経済状況、国際関係、航空路線の回復度合いなど様々な要因に影響され、国・地域によって異なる需要動向を示すと予測されます。以下に主要な国・地域別の需要予測をまとめます。
2025年の中国からのインバウンド需要は、日本にとって引き続き最重要市場であり続けます。2024年までの回復は緩やかだったものの、2025年にはさらに加速し、団体旅行の本格的な再開と個人旅行の増加が期待されます。特に、経済成長に伴う中間所得層の拡大は、旅行需要を押し上げる大きな要因です。
主な旅行目的としては、依然として「買い物」への高い意欲が見られ、特に日本の高品質な日用品、化粧品、電化製品への需要は根強いでしょう。
また、都市部だけでなく、地方の観光地への関心も高まっており、特に温泉地や自然景観が豊かな地域への誘客が重要となります。
懸念材料は、中国経済の先行き不透明感や、地政学的リスクの動向です。しかし、日本と中国間の航空路線がコロナ禍前の水準に近づけば、訪日旅行のコスト低減と利便性向上が進み、需要はさらに押し上げられると見込まれます。
SNSを通じた情報発信が依然として購買行動に強く影響するため、中国の主要プラットフォームを活用したプロモーションが不可欠です。
台湾からのインバウンド需要は、2025年も極めて高い水準を維持すると予測されます。地理的な近接性、親日感情の高さ、そしてリピーターの多さが特徴です。2024年にはコロナ禍前の水準を大きく上回る回復を見せており、2025年もこの勢いは継続するでしょう。
台湾からの旅行者は、日本の「食文化」への関心が非常に高く、特に地方のB級グルメや旬の食材を求めて訪れる傾向が顕著です。また、温泉地、スキーリゾート、桜や紅葉といった四季折々の自然景観も人気です。個人旅行の割合が非常に高く、事前に綿密な計画を立てて、レンタカーなどを利用して広範囲を周遊する傾向が見られます。
SNSでの情報収集が活発であり、友人やインフルエンサーのおすすめが旅行先決定の大きな要因となります。
台湾からの需要を取り込むためには、地方の魅力的なコンテンツ発掘と、多言語対応を含めたきめ細やかな情報提供が重要です。台湾の旅行者の間では、日本の公共交通機関の利便性も高く評価されており、鉄道周遊パスなども引き続き人気の旅行アイテムとなるでしょう。
韓国からのインバウンド需要は、2025年も引き続き堅調に推移すると見込まれます。地理的な近さと航空路線の豊富さ、比較的安価な旅行費用から、週末や短期間の旅行先として日本が選ばれる傾向が強いです。2024年までの回復は非常に早く、コロナ禍前を上回る月もありました。2025年も、特にLCC(格安航空会社)の増便が需要をさらに後押しするでしょう。
主な旅行目的は、「買い物」と「食」が中心ですが、近年は地方のカフェ巡りやアートスポット巡りなど、多様な目的で訪れる層が増加しています。若年層の女性からの支持が特に厚く、SNS映えするスポットや体験が人気を集めます。また、K-POPアイドルやドラマのロケ地巡りなど、ポップカルチャーを起点とした訪日も増加傾向にあります。
旅行形態は個人旅行が主流であり、事前にインターネットやSNSで情報を収集し、効率的に観光地を巡る傾向が強いです。
円安基調が続く限り、韓国からの訪日需要は引き続き高い水準を維持すると考えられますが、日韓関係の安定も重要な要素となります。
東南アジア諸国(特にタイ、ベトナム、インドネシア、マレーシア、フィリピン)からのインバウンド需要は、2025年も高い成長性を示すと予測されます。経済成長による所得水準の向上、中間所得層の拡大、そして各国と日本の航空路線の充実が需要を牽引するでしょう。特に、初めての海外旅行先として日本を選択する層も多く、日本への強い憧れが見られます。
「アニメ・漫画」といったポップカルチャーへの関心が非常に高く、聖地巡礼やイベント参加を目的とした訪日も増加するでしょう。また、「雪景色」や「温泉」といった、自国では体験できない自然や文化への強い関心が見られます。ハラール対応の飲食店や宿泊施設の拡充は、イスラム圏からの誘客に不可欠であり、多様な食文化に対応する柔軟性が求められます。
旅行形態は、個人旅行と団体旅行が混在していますが、近年は個人旅行の割合が増加傾向にあります。SNSの活用が非常に活発であり、インフルエンサーマーケティングや、それぞれの国の言語に合わせた効果的な情報発信が需要獲得の鍵となります。各国間のビザ緩和措置の進展も、今後の需要に大きく影響を与える要因となります。
欧米圏(主に米国、英国、フランス、ドイツ、カナダ、オーストラリアなど)からのインバウンド需要は、高単価かつ長期滞在の傾向が強く、2025年も着実に回復・成長していくと見られます。アジア圏と比較すると回復のペースは緩やかですが、一人当たりの消費額が大きいため、日本全体のインバウンド消費額に与える影響は大きいです。
欧米からの旅行者は、「日本ならではの文化体験」への志向が非常に強く、伝統文化(茶道、華道、武道など)、歴史的建造物、地方の生活文化に触れることを重視します。自然体験(ハイキング、スキー、サイクリングなど)や、食の多様性(ミシュラン星付きレストランから居酒屋、地方の郷土料理まで)も大きな魅力です。
個人旅行が圧倒的に主流であり、事前に綿密な計画を立て、ガイドブックやオンライン情報を活用して旅程を組み立てます。持続可能な観光への意識も高く、環境に配慮した旅行や、地域コミュニティへの貢献を重視する傾向があります。
航空運賃の高止まりが懸念材料ではありますが、富裕層やリピーター層の安定的な来日が期待されます。
情報発信においては、英語を主軸とした質の高いコンテンツ提供と、体験型プログラムの充実が、欧米からの需要獲得には不可欠です。
2025年以降、日本におけるインバウンドの動向は、東京、大阪、京都といったゴールデンルートから地方都市への分散化がより一層加速すると予測されます。これは、オーバーツーリズム問題の顕在化、リピーター層の増加、そして多様な体験を求める旅行者のニーズの高まりが背景にあります。以下に、今後インバウンド需要が高まるであろう注目すべき地方都市を5つ挙げ、その魅力とポテンシャルを解説します。
広島・瀬戸内エリアは、平和記念公園や厳島神社といった世界遺産を擁し、これまでも一定のインバウンド需要がありましたが、今後はより広域での周遊ニーズが高まると予測されます。
瀬戸内海の多島美を活かしたサイクリング(しまなみ海道)やアイランドホッピングといったアクティビティは、欧米豪からのFIT(個人旅行)層に特に響くでしょう。また、アートと自然が融合した直島や豊島などの「アートの島々」は、アジア圏の富裕層や若年層からも高い関心を集めています。
広島・瀬戸内エリアは、広島市内を拠点に、しまなみ海道、尾道、倉敷、さらには愛媛県の道後温泉など、多様な魅力を組み合わせた周遊ルートが提案可能です。地方空港の国際線拡充や、瀬戸内国際芸術祭のような国際的なイベントの継続開催が、さらなる需要喚起に繋がります。
2024年の北陸新幹線敦賀延伸により、東京からのアクセスがさらに向上した金沢・北陸エリアは、今後本格的なインバウンドブームが期待されます。
金沢は「兼六園」や「ひがし茶屋街」に代表される伝統文化、そして新鮮な海の幸が魅力であり、特に欧米からの富裕層や文化体験を重視する層に人気です。さらに、能登半島地震からの復興が進めば、能登の里山里海の文化への注目も高まるでしょう。加えて、世界遺産の白川郷や五箇山の合掌造り集落、立山黒部アルペンルート、さらに温泉地が点在するなど、多様な自然と文化体験が可能です。
これらの周辺エリアと連携した広域観光ルートの造成と、多言語での情報発信強化が、リピーターや新規客の誘致に繋がります。
沖縄本島北部の「やんばる」エリアは、2021年に世界自然遺産に登録されたことで、エコツーリズムやアドベンチャーツーリズムを求める欧米豪やアジア圏の富裕層からの注目度が高まっています。これまで那覇市や南部が中心だった沖縄観光において、手つかずの自然が残るやんばるは、新たな体験価値を提供できるフロンティアです。トレッキング、カヌー、星空観測など、沖縄の豊かな自然を体験できるアクティビティの充実が期待されます。2025年7月25日には、大自然没入型のテーマパーク「ジャングリア沖縄」のオープンも控えています。
ただし、世界遺産エリアであるため、持続可能な観光モデルの構築が不可欠です。オーバーツーリズムを避け、地域住民との共生を図りながら、自然環境への配慮を徹底した観光開発とプロモーションが求められます。
札幌を中心とした道央エリアは、ニセコの世界有数のパウダースノーが欧米豪のスキーヤー・スノーボーダーを惹きつけ、すでに国際的なリゾート地としての地位を確立しています。今後は、ニセコだけでなく、富良野や美瑛といった夏場のラベンダー畑や美しい景観が、アジア圏を中心に新たな需要を喚起すると見られます。アウトドアアクティビティの多様性(ラフティング、サイクリング、ゴルフなど)と、広大な自然の中で育まれた食の魅力(ジンギスカン、スープカレー、乳製品など)が、通年での滞在を促す要素となります。
新千歳空港の国際線ネットワークの更なる拡充と、四季折々の魅力を効果的に発信するプロモーション戦略が、さらなるインバウンド誘致の鍵となるでしょう。
東北地方は、これまで震災の影響もありインバウンド回復が遅れていましたが、今後は豊かな自然、奥深い歴史・文化、そして冬の美しい雪景色が、欧米豪やアジア圏のリピーター層に響くと予測されます。特に仙台を拠点に、松島や蔵王といった景勝地、平泉のような世界遺産、そして豊富な温泉地が点在しています。青森のねぶた祭や秋田の竿燈まつりなど、東北ならではの力強い伝統祭りは、体験型消費を求める旅行者にとって大きな魅力となります。また、雪質が良いスキー場も多く、ウィンタースポーツ愛好家にとっても魅力的なエリアです。
東北地方全体での広域連携による周遊ルートの造成と、外国人旅行者向けの交通パスの充実、そして食の魅力を前面に出したプロモーションが、今後のインバウンド需要を大きく押し上げるでしょう。
2025年以降の訪日旅行市場において、単なる観光地の羅列や買い物だけでは、もはや旅行者の心を掴むことはできません。旅行者はより深く、より本質的な「体験」を求めており、そのキーワードとなるのが「文化」「食」、そして「サステナブル」です。
訪日旅行者が求める「文化」体験は、単に歴史的建造物を見るだけでなく、「その文化を肌で感じる」「地元の人々と交流する」ことに重点が置かれています。例えば、京都の舞妓さんの踊りを鑑賞するだけでなく、茶道体験で自らお茶を点て、その作法や精神に触れること。武道体験で日本の精神性を学び、座禅体験で心を整えること。また、伝統工芸(陶芸、染物、和紙など)の制作体験を通じて、職人の技やものづくりへのこだわりを理解することも人気です。祭りの時期に訪れて、地域の人々と一体となって参加することで、その土地の活気や伝統を深く体験したいというニーズも高まっています。さらに、アニメや漫画といったポップカルチャーの聖地巡礼も、現代の重要な文化体験の一つとして定着しており、関連イベントへの参加意欲も非常に高いです。これらの体験は、SNSで共有されることで、さらなる誘客に繋がる傾向にあります。
訪日旅行者にとって、「食」は単なる食事を超えた「究極の体験」です。ミシュランガイドに掲載されるような高級料理だけでなく、地方独自の郷土料理やB級グルメ、さらにその食材がどのように生産され、調理されるのかといった背景にまで関心が寄せられています。例えば、漁港の朝市で新鮮な魚介類を味わい、地元農家が営むレストランで旬の野菜を堪能すること。日本酒や焼酎の酒蔵見学と試飲を通じて、その土地の水や風土が育む味わいの奥深さを知ること。屋台や居酒屋での地元の人々との交流も、食を通じた貴重な体験となります。また、精進料理やヴィーガン対応、ハラール対応など、多様な食文化を持つ旅行者のニーズに応えることの重要性も増しています。食体験は、地域の魅力そのものであり、食をフックにした周遊ルートの造成や、食にまつわるイベントの開催が、インバウンド誘致の強力な武器となります。
近年、訪日旅行者の間で「サステナブルツーリズム(持続可能な観光)」への意識が急速に高まっています。これは、環境負荷の低減、地域経済への貢献、そして文化や伝統の尊重を重視する旅のスタイルです。例えば、公共交通機関の積極的な利用、環境に配慮した宿泊施設の選択、プラスチックごみの削減への協力などが挙げられます。また、地域住民との交流を深める体験(農作業体験、古民家での滞在など)や、地元の特産品を購入することで地域経済を支援することも、サステナブルな旅の一部として捉えられています。世界遺産や国立公園などの自然豊かな地域では、自然保護への貢献や、エコツーリズムに参加することで、責任ある観光を実践したいというニーズも顕在化しています。観光事業者にとっては、持続可能性への取り組みを明確に示し、旅行者にその意義を伝えることが、選ばれるデスティネーションとなるための重要な要素となります。
2025年のインバウンド市場は、単なる需要回復を超え、旅行者のニーズの多様化と持続可能性への意識の高まりを背景に、新たな局面を迎えています。企業・自治体は、この変化を捉え、より戦略的なアプローチを取ることが成功の鍵となります。以下に、取るべき主要な戦略を解説します。
もはや一律の「おもてなし」だけでは不十分です。各企業・自治体は、ターゲットとする国・地域の旅行者層(例:欧米豪の富裕層、アジアの若年層、ファミリー層、リピーター層など)を明確にし、彼らが求める「体験」に特化したコンテンツを開発する必要があります。具体的には、伝統文化体験(茶道、着物、武道など)の深化、地域独自の食文化体験(農泊、酒蔵見学、郷土料理教室など)、自然体験(トレッキング、サイクリング、星空観測など)の充実が挙げられます。さらに、アニメや漫画の聖地巡礼、eスポーツイベントとの連携、ワーケーション需要に対応した長期滞在プランなど、現代的なトレンドを取り入れた多様な切り口も重要です。既存の観光資源を見直し、外国人目線で新たな魅力を発掘し、ストーリー性を持たせたパッケージ化を進めることが求められます。
インバウンド戦略において、デジタル技術の活用は不可欠です。各企業・自治体は、ターゲットとする国・地域の主要SNS(WeChat、小紅書、Instagram、Facebookなど)や旅行系プラットフォーム(TripAdvisor、Booking.comなど)を徹底的に分析し、それぞれの特性に合わせた多言語での情報発信を行う必要があります。単なる翻訳ではなく、文化的な背景を理解した上で魅力が伝わるコンテンツ(動画、写真、記事など)を作成することが重要です。また、観光施設の公式サイトや予約システムは、多言語対応はもちろんのこと、スマートフォンからの利用を想定したUI/UXの最適化が不可欠です。AI翻訳やチャットボットの導入による多言語での問い合わせ対応、キャッシュレス決済の多様化、無料Wi-Fi環境の整備など、旅行者の利便性を徹底的に追求することで、ストレスフリーな旅を提供できます。
オーバーツーリズム問題への懸念が高まる中、企業・自治体は持続可能な観光への取り組みを明確に打ち出すことが求められます。これは単なるCSR活動ではなく、欧米豪の旅行者を中心に「責任ある旅行」を志向する層への訴求力を高める戦略でもあります。具体的には、地域住民との共生を促すような観光モデルの構築(例:住民生活圏への配慮、地域イベントへの外国人参加促進)、環境負荷の低減(例:公共交通機関利用の推奨、ゴミの分別徹底、エコフレンドリーな宿泊施設の推進)、そして地域経済への貢献(例:地元産品の積極的な利用、地域住民の雇用創出)を実践し、その取り組みを積極的に情報発信することが重要です。「地域に還元される観光」という明確なメッセージを打ち出すことで、新たな顧客層を獲得し、長期的な関係性を築くことができます。
ゴールデンルートへの集中を避けるため、地方都市へのインバウンド分散化は喫緊の課題です。これには、単一の企業や自治体だけでなく、周辺地域との広域連携が不可欠です。複数の魅力的な観光地を結ぶ「周遊ルート」を共同で開発・プロモーションすることで、旅行者の長期滞在や消費拡大を促します。具体的には、テーマ性のある観光ルート(例:温泉巡り、アート巡り、歴史街道巡りなど)を設定し、共同で情報発信を行います。また、地方へのアクセスを容易にするため、二次交通(バス、レンタカー、タクシー、鉄道など)の多言語対応や情報提供の強化、地域内での移動を円滑にするためのアプリ開発なども重要です。地方空港の国際線誘致や増便への働きかけも、広域連携の中で積極的に推進すべきです。
インバウンド需要の増加に伴い、観光産業における人手不足は深刻な課題です。企業・自治体は、労働環境の改善やDXによる業務効率化を進めるとともに、多様な国籍の人材を受け入れ、育成する体制を構築する必要があります。外国人留学生や特定技能外国人材の積極的な採用、多言語対応が可能な日本人スタッフの育成、そして多文化共生社会の実現に向けた啓発活動が求められます。外国人スタッフが働きやすい環境を整備することは、サービス品質の向上だけでなく、顧客である外国人旅行者への理解を深める上でも極めて重要です。地域全体で外国人住民との交流を促進し、多様な価値観を尊重する社会を築くことが、真のインバウンド対策に繋がります。
2025年からのインバウンド需要は、これまでの回復期を経て新たな局面を迎えつつあります。パンデミック前の水準に回復するだけでなく、旅行者のニーズはより多様化し、本質的な「体験」を求める傾向が強まっているからです。これからは、ーバーツーリズムの回避や、日本の奥深い魅力を求めるリピーター層の増加から東京や大阪といった大都市だけでなく、地方都市を訪れるインバウンド客が飛躍的に増加することが予想されます。
この変化の波に乗り遅れないよう、企業や自治体は今こそブームを先取りし、戦略的なインバウンド対策を進めましょう。インバウンド需要を取り込むには、地方ならではの文化や食、自然体験に特化したコンテンツ開発、そして多言語対応やデジタル技術を駆使した情報発信が不可欠です。持続可能な観光モデルを構築して地域住民との共生を図り、長期的な視点での集客最大化を目指しましょう。
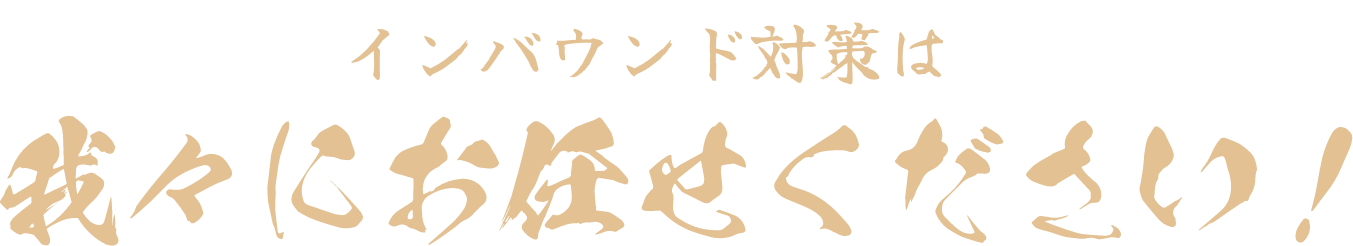
私たち、インバウンドマーケティングジャパンは、
訪日外国人観光客の集客支援に”とんでもなく”特化。
多言語対応のMEOやGoogle広告を活用したデジタルマーケティングの知見を生かし、訪日客の集客や来店促進、海外向けSNSの構築・運用、店舗のインバウンド対応まで、総合的な支援サービスを行っています。
「対策を進めたいが、どこから手をつけていいか分からない」とお困りですか?当社では、企業や店舗様の課題と目標に合わせた最適なプランをご提案いたします。無料での相談も受け付けていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください!