
【目次】
小紅書(RED)は、中国の若年層、特に女性を中心に絶大な人気を誇るソーシャルコマースプラットフォームです。2013年に創業し、当初は海外の高品質な商品を共有するコミュニティとしてスタートしましたが、現在では美容、ファッション、旅行、グルメなど多岐にわたるライフスタイル情報を発信する巨大SNSへと発展しました。ユーザーは商品のレビューを投稿したり、他のユーザーのレビューを参考に商品を購入したりと、情報収集から購買までを一貫して行えるのが特徴です。ここでは、小紅書(RED)の基本機能と特徴を解説します。
小紅書(RED)は、以下の主要な機能を通じてユーザーに多様な体験を提供しています。
小紅書(RED)が中国で絶大な影響力を持つ理由は、その独特な特徴にあります。小紅書(RED)は「UGC(User Generated Content)」中心のプラットフォームで、ユーザー自身が作成するレビューや体験談がコンテンツの中心であるという特徴があります。
小紅書(RED)のユーザーは、新しいトレンドに敏感な20代~30代の女性が中心です。彼女たちは美容やファッションへの関心が高く、情報収集から購買までの導線がスムーズであるため、企業にとっては強力なマーケティングツールとなりつつあります。
また、小紅書(RED)は精度の高いレコメンド機能を備えているのも特徴です。ユーザーの閲覧履歴や「いいね」に基づき、パーソナライズされたコンテンツを推薦する機能が非常に優れているため、ユーザーは自分の興味に合った情報を効率的に発見できます。
インフルエンサー(KOC/KOL)の影響力も無視できません。小紅書(RED)には「KOC(Key Opinion Consumer)」と呼ばれる一般のユーザーや、「KOL(Key Opinion Leader)」と呼ばれるプロのインフルエンサー多数登録しており、彼らの発信する正直なレビューや使用体験が、商品の売上を大きく左右することがあります。
単なる情報共有プラットフォームに留まらず、情報収集から購買までのユーザー体験がシームレスなためなり、中国市場への参入を目指す企業にとって、消費者との接点を生み出し、ブランド認知度を高め、売上を向上させるための非常に有効なプラットフォームといっても過言ではありません。
特にそのUGC中心の特性と購買意欲の高いユーザー層は、他SNSにはない独自の強みと言えるでしょう。
小紅書(RED)は、美容やファッションだけでなく、実は飲食店集客においても非常に強力なプラットフォームとして知られています。その理由は、以下の点に集約されます。
小紅書(RED)の最大の特徴であるUGC(User Generated Content)の質の高さは、飲食店の集客においても効果を発揮します。ユーザーは、訪れた飲食店の料理の見た目、店内の雰囲気、サービス、そして正直な感想を写真や動画、テキストで詳細に共有します。単なるメニュー紹介ではなく、「この料理は〇〇と一緒に食べると美味しい」「この時間帯が空いている」「デートにおすすめ」といった、具体的な体験談やシチュエーションが豊富に投稿されることで、他のユーザーは実際に自分がその店を訪れた際のイメージを具体的に持つことができ、来店意欲が高まります。
小紅書(RED)の主要ユーザー層である20代~30代の女性は、友人との食事や記念日、女子会といったシーンで「どこに行こうか」「何を食べようか」とSNSで情報収集する傾向が非常に強いとされています。そのため、見た目の美しさや写真映えする料理、おしゃれな空間を売りにする飲食店のターゲット層と小紅書(RED)ユーザーの属性が重複しやすく、小紅書(RED)を利用することで店舗の魅力を広くPRできます。
小紅書(RED)のレコメンド機能は、ユーザーの過去の閲覧履歴や「いいね」に基づき、パーソナライズされた飲食店情報を提供します。「〇〇(地名) おしゃれカフェ」「〇〇(料理名) おすすめ」「デートスポット」といった具体的なキーワードで検索されることも多く、ユーザーは自分の興味や目的に合った飲食店を効率的に見つけることができます。これにより、まだ知られていない隠れた名店や、特定のジャンルに特化した飲食店も、適切なユーザー層にリーチしやすくなります。
近年、小紅書(RED)でもライブ配信やショート動画の機能が強化されています。飲食店は、料理が作られる過程や、店内の活気ある様子、シェフのこだわりなどを視覚的に魅力的に伝えることができるのが強みです。ライブ配信中に試食会を行ったり、限定クーポンを配布したりすることで、ユーザーの来店を直接的に促すこともできます。テキストや静止画だけでは伝わりにくい飲食店の魅力を、多角的にアピールできる点も、集客に繋がるでしょう。
新型コロナウイルス感染症の収束後、訪日中国人観光客が急速に回復する中、今こそ小紅書(RED)を活用することが、日本企業にとって喫緊の課題となっています。特にインバウンド市場における中国人観光客の動向を踏まえると、小紅書(RED)は単なるSNSではなく、集客と売上を最大化するための不可欠なツールと化しています。ここからは、インバウンド市場と中国人観光客の動向も踏まえながら、小紅書(RED)を使うべき理由を解説します。
日本政府観光局(JNTO)のデータが示す通り、訪日外国人観光客数は着実に回復しており、中でも中国人観光客の回復は顕著です。彼らは購買意欲が高く、日本での「体験」や「質の高い商品」を強く求めています。特筆すべきは、彼らが旅行計画段階から情報収集にSNSを多用し、特に小紅書(RED)を主要な情報源としている点です。伝統的なガイドブックや旅行会社の情報だけでなく、リアルなユーザーの体験談やレビューを重視する傾向が非常に強く、小紅書(RED)はそのニーズに最も合致しています。
中国人観光客の多くは、旅行前から小紅書(RED)で「日本 旅行 おすすめ」「東京 グルメ」「大阪 買い物」といったキーワードで検索し、具体的な訪問先や購入商品を検討します。小紅書(RED)上で「映える」写真や動画、詳細なレビューが投稿されている店舗や商品は、彼らの「行きたい」「買いたい」という購買意欲をダイレクトに刺激します。滞在中も、小紅書(RED)でリアルタイムに情報検索を行い、近くの飲食店や人気スポットを訪れるといった行動が見られます。つまり、小紅書(RED)は単なる情報共有の場ではなく、訪日中国人観光客の「情報収集」から「意思決定」、さらには「購買」までを一貫してサポートするプラットフォームなのです。
小紅書(RED)は、日本の地方の魅力や隠れた名店、独自の体験などを中国人観光客に伝える上で、極めて有効なツールです。既存の観光ルートだけでなく、小紅書(RED)上で特定のテーマ(例:アニメ聖地巡礼、日本の伝統工芸体験、地域のB級グルメなど)に特化したコンテンツを発信することで、新たな観光需要を掘り起こすことができます。また、企業や自治体が公式アカウントを開設し、質の高いコンテンツを継続的に発信することで、ブランドイメージを構築し、信頼性を高めることが可能です。ユーザーが投稿するUGCは、その企業の「生きた口コミ」となり、強力なプロモーション効果を生み出します。
今後、訪日中国人観光客の誘致競争はますます激化すると予想されます。その中で、小紅書(RED)を積極的に活用することは、競合他社との差別化を図る上で不可欠です。小紅書(RED)上で魅力的な情報を発信し、中国人ユーザーとのエンゲージメントを高めることで、他にはない独自の集客チャネルを確立できます。さらに、小紅書(RED)内のライブコマース機能などを活用すれば、越境ECと連携し、帰国後も継続的に商品を購入してもらうといった新たなビジネス機会を創出することも夢ではありません。今、小紅書(RED)を使わないことは、最大の顧客層の一つである中国人観光客との接点を失うことを意味すると言っても過言ではないでしょう。
小紅書(RED)をはじめとする中国SNSでの情報発信において、中国人インフルエンサー(KOL:Key Opinion Leader)の活用は、中国人集客の成否を分ける重要な要素となります。特に、日本在住の中国人KOL(在日KOL)は、日本の文化や商品、サービスへの理解が深く、中国の最新トレンドも把握しているため、より効果的な情報発信が期待できるでしょう。ここからは、中国人集客のカギを握る在日KOLの活用法を解説します。
在日KOLは、単にフォロワーが多いだけでなく、中国人フォロワーとの間に深い信頼関係を築いている点が強みです。
在日KOLは、日本での生活を通じて得たリアルな情報や体験を共有している点が、在外インフルエンサーとの大きな違いです。彼らは日本の流行、穴場スポット、商品の使用感など、中国人観光客が求める「生の声」を発信できるため、日本旅行を計画している中国人に「信頼できる情報を発信してくれる」と思われています。
また、日本と中国双方の文化やトレンドを理解しているため、中国人フォロワーが共感しやすい表現や、響くコンテンツを企画・制作できるのも強みです。日本の商品の魅力を中国語で的確に伝えてくれるため、「私も行ってみたい」「これを買ってみたい」という具体的な行動に繋がりやすいという特徴があります。
効果的なKOLマーケティングを行うためには、適切なKOLを選定することが重要です。選定する際は、次のポイントをチェックしましょう。
選定したKOLを最大限に活用するための施策を計画しましょう。KOLにPRを依頼するにあたっては、次のような施策が広く実施されています。
小紅書(RED)での飲食店プロモーションを成功させるためには、プラットフォームの特性を理解し、中国人ユーザーの心に響くコンテンツを作成することが不可欠です。以下に、小紅書(RED)を運用する際の重要なポイントを解説します。
小紅書(RED)は「映え」が重視されるプラットフォームであり、写真や動画のクオリティは投稿の成否を大きく左右します。写真や動画を撮影する際は、次のことを意識しましょう。
単に美しい写真だけでなく、ユーザーが来店を検討する上で役立つ具体的な情報を提供することが重要です。自分がユーザーだったらどんな情報が知りたいか考えながら、投稿文を作成しましょう。
投稿が多くのユーザーの目に触れるためには、適切なハッシュタグとキーワードの選定が不可欠です。ハッシュタグを選定する際は、小紅書(RED)内の流行タグもチェックすることが重要です。
小紅書(RED)はコミュニティ機能が強いため、ユーザーとのコミュニケーションが重要です。レビューへの返信はもちろん、レビュー投稿を呼びかけるなどして質の高いUGCを集めてください。
小紅書(RED)は強力な集客ツールですが、その効果を最大限に引き出すためには、オンラインとオフラインを組み合わせた戦略が不可欠です。具体的には小紅書(RED)単体での情報発信に加え、在日KOLの活用、ユーザー参加型のイベント、利便性を高めるオフライン連携といった「+α」の戦略が、中国人観光客の集客を成功させるカギとなります。
ここからは、小紅書(RED)を活用して集客を増加させたモデルケースを2つご紹介します。
東京の観光地にある老舗の抹茶カフェ「A」は、伝統的な日本の雰囲気を保ちつつも、小紅書(RED)を活用して若い中国人観光客の集客に成功しました。
この店舗は、美しい抹茶ラテや季節限定の和スイーツの「映える」写真と動画を積極的に小紅書(RED)に投稿しました。特に、熟練の職人が抹茶を点てる様子や、美しい庭園を背景にしたカフェの動画は大きな反響を呼びました。投稿では、使用する抹茶の産地やこだわり、和菓子の手作り感を強調し、日本の「匠の技」と「おもてなし」を伝えました。
そのうえで、+αの施策として次のことを実践しました。
これらの複合的な戦略により、「A」は小紅書(RED)上で「東京抹茶巡り」の定番スポットとして認知されるようになり、中国人観光客の来店数が前年比で約2倍に増加しました。特に、KOLが発信した情報を見たという新規顧客が多く見られました。
大阪の繁華街にある体験型たこ焼き店「B」は、ただたこ焼きを提供するだけでなく、顧客が自らたこ焼きを焼けるユニークなコンセプトが特徴です。小紅書(RED)とオフライン施策を組み合わせ、集客を大幅に伸ばしました。
まず「B」は、お客さんが楽しそうにたこ焼きを焼いているショート動画を小紅書(RED)に投稿することに注力しました。特に、家族や友人と協力してたこ焼きを作る様子、失敗しても笑顔で楽しむ姿などが共感を呼びました。投稿では、「大阪旅行の思い出作り」「体験型グルメ」といったキーワードを使い、単なる食事ではなく「特別な体験」であることを強調しました。
そのうえで、次の施策も実施しました。
この結果、「B」は小紅書(RED)上で「大阪でしかできない体験」として急速に認知度を高め、特に若年層の中国人観光客からの予約が殺到しました。体験予約数は小紅書(RED)導入前と比較して3倍近くに増加し、リピーターも増えるなど、大きな集客効果を上げています。
中国人からの訪日客を呼び込むには、彼らが情報収集の主要ツールとして利用する小紅書(RED)の活用が不可欠です。単に店舗の情報を投稿するだけでなく、より効果的な集客のためには、「生の声」の発信が重要になります。
その鍵を握るのが、在日KOLとの積極的な連携です。彼らは日本の生活や文化、流行に精通しており、フォロワーとの間に深い信頼関係を築いています。在日KOLによるリアルな体験談やレビューは、通常の広告よりもはるかに強い説得力を持ち、中国人ユーザーの「行きたい」「買いたい」という購買意欲を直接刺激します。
小紅書(RED)運用やKOL連携に自信がない場合は、インバウンド集客に強みを持つマーケティング会社や専門家のサポートを検討するのも有効な手段です。プロの知見とノウハウを活用することで、より効率的かつ効果的に中国人観光客へのアプローチが可能となり、インバウンド集客を加速させることができるでしょう。
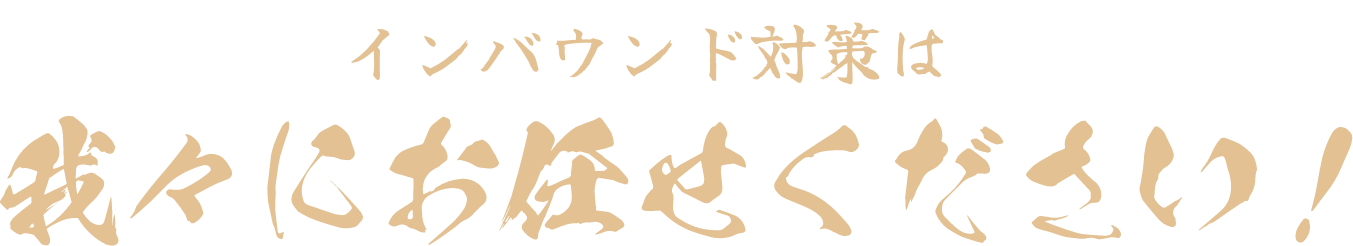
私たち、インバウンドマーケティングジャパンは、
訪日外国人観光客の集客支援に”とんでもなく”特化。
多言語対応のMEOやGoogle広告を活用したデジタルマーケティングの知見を生かし、訪日客の集客や来店促進、海外向けSNSの構築・運用、店舗のインバウンド対応まで、総合的な支援サービスを行っています。
「対策を進めたいが、どこから手をつけていいか分からない」とお困りですか?当社では、企業や店舗様の課題と目標に合わせた最適なプランをご提案いたします。無料での相談も受け付けていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください!