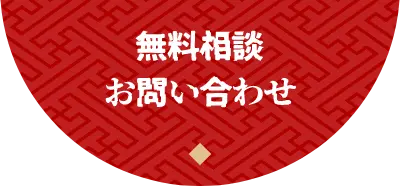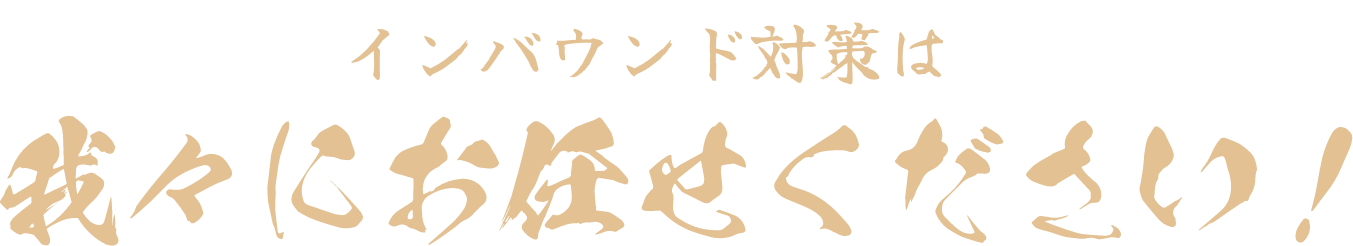ショート動画で外国人にバズる!15秒でシズル感を伝え、来店に繋げる飲食店PR動画の作り方
【目次】
なぜ今、飲食店の「ショート動画」が外国人に刺さるのか?
近年、飲食店のショート動画がインバウンド客に絶大な人気を博しています。これは単なる一過性のトレンドではなく、現代の旅行スタイルや情報収集の変化、そしてショート動画が持つ特性が巧みに融合した結果と言えるでしょう。ここからは、ショート動画が外国人観光客に刺さる理由を解説します。
はい、承知いたしました。各項目を400字程度にリライトします。
1. 視覚と聴覚に訴えかける没入感
飲食店のショート動画が持つ最大の魅力は、その圧倒的な没入感です。単なる写真では伝えきれない、料理が目の前で調理されるシズル感、立ち上る湯気、鮮やかな盛り付け、そして食欲をそそる音のすべてを、短い動画の中で凝縮して体験できます。まるで実際にその場にいるかのような「ライブ感」は、視聴者の五感を刺激し、強く印象に残ります。SNSのアルゴリズムが、ユーザーの興味関心に合わせて次々と関連動画を表示する仕組みも、この没入感をさらに深める要因です。これにより、外国からの観光客は、ただ料理を見るだけでなく、その場の雰囲気やエネルギーまでをも感じ取り、「この店に行きたい」「この料理を味わいたい」という強い衝動に駆られるのです。
2. 言語の壁を越える普遍性
ショート動画は、言葉の壁を軽々と乗り越える普遍的な情報伝達手段として、インバウンド客にとって非常に有効です。日本語が分からなくても、美味しそうな料理の映像を見れば、その魅力が直感的に伝わります。複雑なメニューの説明を読んだり、翻訳アプリを使ったりする手間を省き、視覚情報だけで「食べてみたい」「行ってみたい」という感情をダイレクトに喚起させることが可能です。
これは、多様な言語を話す世界中の旅行者に対し、店の魅力を効果的にアピールする上で不可欠な要素と言えます。言語の障壁がないからこそ、多くの外国人が躊躇なく情報を収集し、日本での食体験への期待感を高めることができるのです。
3. 手軽な情報収集と意思決定
多忙な旅行中のインバウンド客にとって、限られた時間の中で効率的に情報を収集し、食事場所を決めることは重要です。ショート動画は、まさにそのニーズにぴったり合致します。わずか数秒から数十秒という短い時間で、店の雰囲気、提供される料理の種類、人気メニューなどを総合的に把握できるため、非常に効率的な情報源となります。InstagramのリールやTikTokといったプラットフォームで手軽に検索・発見できる点も、利用を促す大きな要因です。文字情報を読み込むよりも視覚的に素早く判断できるため、外国人旅行者は時間を無駄にすることなく、自身の興味に合った飲食店を簡単に見つけ出し、スムーズに次の行動へと移ることができるのです。
4. 「体験」への共感と共有欲求
現代の旅行者は、単なる観光地巡りだけでなく、その土地ならではの「特別な体験」を重視します。飲食店のショート動画は、美味しそうな料理だけでなく、活気ある店内の様子、店員の温かい接客、楽しそうに食事をする他のお客さんの姿など、その場所で得られるであろう「食を通じた体験」を疑似的に提供します。この動画が喚起する共感は、「自分も同じ体験をしてみたい」という強い来店動機に繋がります。さらに、その体験を自身のSNSで友人やフォロワーと共有したいという欲求も高まります。ショート動画によって刺激されたインスピレーションが、来店後の「#(ハッシュタグ)」付き投稿を促し、それが新たなインバウンド客の来店に繋がるという、素晴らしい拡散の連鎖を生み出しているのです。
訪日外国人観光客の動画サイト・SNS利用率
訪日外国人観光客にとって、動画サイトやSNSはもはや旅行の情報収集に欠かせないツールとなっています。その利用率は非常に高く、多くの旅行者が旅行計画の段階から、そして滞在中も積極的に活用しているのが現状です。
観光庁の調査によると、訪日外国人が旅行の出発前に役立った情報源として、SNSが約25%・動画サイトが約21%を占めており、その重要性がうかがえます。特に、InstagramやYouTube、TikTokなどの視覚情報が中心のプラットフォームは、言語の壁を越えて直感的に魅力を伝えられるため、国籍を問わず幅広く利用されているのが現状です。
例えば、香港からの訪日客は約65%、米国からの訪日客は約70%がInstagramを利用しているというデータもあります。
動画サイトであるYouTubeは、詳細な旅行プランや具体的な体験の紹介に適しており、「#japantrip」や「#tokyotravel」といったハッシュタグを使って、多くのユーザーが情報を検索しています。また、Instagramは視覚的な魅力の訴求や認知拡大に強く、美しい写真や短い動画を通じて、日本の観光地やグルメ、文化体験が共有されています。
訪日外国人観光客は、ガイドブックやパンフレットには載っていないリアルでニッチな情報を求めており、SNS上の口コミやインフルエンサーによる投稿を重視する傾向があります。旅先での体験を「映え」る写真や動画としてSNSに投稿し、それを友人やフォロワーと共有する文化も浸透しているため、SNSは情報収集だけでなく、体験の共有と拡散の場としても機能しています。
YouTube Shorts・TikTok・Instagramの違いと特性
ショート動画が主流となる現代において、YouTube Shorts、TikTok、Instagramはそれぞれ異なる特性を持ち、ユーザーの利用目的やコンテンツの傾向に違いが見られます。それぞれの特徴を解説します。
YouTube Shorts
YouTube Shortsは、世界中のユーザーが利用するYouTubeのエコシステム内に組み込まれたショート動画機能です。その最大の利点は、既存のYouTubeの膨大なユーザー基盤と、長尺動画とのシームレスな連携にあります。視聴者は、興味を引くショート動画を発見した際に、同じクリエイターが投稿している関連の長尺動画へと簡単にアクセスできます。これにより、単なる短いエンターテインメントに留まらず、より深く、詳細な情報や知識を得ることが可能です。
この特性から、YouTube Shortsでは情報の深掘りや専門性の高いコンテンツが多く見られます。例えば、特定のスキルに関するチュートリアル、複雑なトピックの要約、製品レビューのダイジェストなどが人気です。また、YouTubeが長年にわたり培ってきた収益化の仕組みがショート動画にも適用されるため、クリエイターは安定した活動を継続しやすく、質の高いコンテンツを持続的に生み出すモチベーションに繋がっています。
幅広い年齢層にリーチできる汎用性の高さも特徴で、教育系からエンタメ系まで、多様なジャンルのクリエイターが自身のコンテンツを効果的にアピールできる場となっています。
TikTok
TikTokは、短時間で「バズる」コンテンツを生み出すことに特化した、独特のプラットフォームです。その核となるのは、ユーザーの興味関心に合わせて最適化された「おすすめ」フィードと、誰でも簡単にプロのような動画を作成・編集できる直感的なツール群です。流行のBGMやエフェクトを駆使した、短く、キャッチーで、思わず繰り返し見てしまうようなエンターテインメント性の高い動画が主流を占めています。
特に若年層からの絶大な支持を得ており、ダンスチャレンジ、日常生活のコミカルな瞬間を切り取ったミーム、ユーザー参加型のハッシュタグチャレンジなどが次々と生まれ、爆発的に拡散されています。
TikTokのアルゴリズムは、ユーザーの視聴履歴やインタラクションから嗜好を驚くほど素早く学習し、「次に何を見たいか」を正確に予測して関連性の高いコンテンツを提示し続けるのが特徴です。これにより、ユーザーは飽きることなく長時間アプリを利用し続ける傾向があります。
トレンドの創出と拡散力が非常に高く、瞬く間に社会現象となるようなコンテンツが生まれる点が、他のプラットフォームとは一線を画すTikTok最大の特性と言えるでしょう。
Instagramは、もともと「写真で世界を共有する」というコンセプトから始まり、ビジュアルの美しさやライフスタイルを重視したコンテンツが中心のプラットフォームです。近年、リール機能の登場によってショート動画が普及しましたが、それでもユーザーは依然として投稿の「映え」や「統一された世界観」を強く意識する傾向にあります。
そのため、Instagramではファッション、美容、グルメ、旅行、インテリアといった、視覚的に魅力的でインスピレーションを与える分野のコンテンツが特に人気です。
多くのブランドやインフルエンサーが、製品やサービスの世界観を表現するためにInstagramを活用し、洗練されたビジュアルを通じてフォロワーとのエンゲージメントを高めています。
投稿へのコメントや「いいね!」はもちろん、ストーリーズやダイレクトメッセージ(DM)といった機能を活用することで、フォロワーとのより密なコミュニケーションが図りやすいのも特徴です。流行に敏感なユーザーが多く、トレンドのキャッチアップや情報収集にも利用されることが多いため、「憧れ」や「共感」を軸としたコンテンツ発信において強力なプラットフォームとなっています。
外国人にバズるショート動画のポイント
訪日外国人観光客に響き、SNSで拡散される「バズる」ショート動画には、いくつかの共通するポイントがあります。単に美味しそうな料理を映すだけでなく、文化的な背景や体験を意識したコンテンツが重要です。ここからは、外国人にバズる動画のポイントを解説します。
1. 「日本らしさ」の際立つビジュアルと演出
訪日外国人が日本へ求めるのは、単なる観光ではなく、異文化との出会いと体験です。そのため、飲食店のショート動画では、視覚的に「日本らしさ」が伝わる要素を強く打ち出すことが非常に重要になります。例えば、伝統的な日本家屋のたたずまい、繊細な意匠が施された和食器、熟練の職人が魅せる手仕事、あるいは桜、紅葉、雪景色といった四季折々の日本の美しい風景を背景にした飲食シーンは、外国人視聴者に「これぞ日本」という印象を強く与えます。
料理の盛り付けにおいても、単に美味しそうに見せるだけでなく、色彩の調和や器との組み合わせなど、芸術的な「和」の美意識を意識すると良いでしょう。こうした演出は、料理の味覚だけでなく、日本の文化や美学への興味を喚起し、特別な体験として記憶に残ります。単なるグルメ紹介に終わらず、「日本ならではの文化的な魅力」を視覚的に表現することで、外国人視聴者の心を深く掴み、来店への強い動機付けとなるでしょう。
2. シズル感とライブ感の追求
料理のショート動画において、視聴者の食欲を直感的に刺激する「シズル感」は、言語の壁を越える最も強力な要素です。湯気が立ち上る温かいラーメン、熱々の鉄板でジュージューと音を立てるステーキ、とろりと伸びるチーズ、衣がサクッと揚がる天ぷらなど、五感を刺激する映像は、見る者の食欲を最大限に掻き立てます。
さらに重要なのは、単に完成した料理を美しく映すだけでなく、調理の過程や、実際に食べる瞬間のリアルな反応を捉えることです。一口食べた瞬間の「うまい!」という表情や声、咀嚼音、調理中の心地よい音など、「ライブ感」を演出する要素を盛り込むことで、視聴者はまるでその場にいるかのような臨場感を味わえます。この没入感こそが、動画を見た人に「自分もこの味を体験したい」という強い欲求を抱かせ、実際の来店へと繋がる強力な動機付けとなるのです。音響効果を巧みに利用し、映像と音の両面から食欲を刺激する工夫が不可欠です。
3. ストーリー性やキャラクター性
単に料理の映像を羅列するだけでは、多くのショート動画の中に埋もれてしまいがちです。外国人の心に深く刺さり、記憶に残る動画にするためには、短いながらも心温まる「ストーリー性」を持たせることが非常に効果的です。例えば、料理人が食材を厳選する真摯な姿勢、料理への並々ならぬ情熱、あるいは店主と常連客との微笑ましい交流など、その店独自の人間ドラマを感じさせる要素は、視聴者の共感を呼びます。
「この店にはこんな素敵な背景があるのか」と感じさせることで、単なる飲食店ではなく、訪れる価値のある場所として認識され、来店への動機付けが格段に強まります。さらに、店の名物である店主やユニークな個性を持つ店員など、「キャラクター」を登場させることも、動画に親しみやすさと人間味を与え、視聴者の記憶に深く刻まれる要因となります。親しみやすいキャラクターは、動画のエンゲージメントを高め、長期的なファンを獲得する上でも非常に有効な戦略です。
4. 体験型要素の提示と参加意欲の喚起
現代の訪日外国人観光客は、単に有名な観光地を巡るだけでなく、その土地ならではの「特別な体験」を強く求めています。飲食店のショート動画においても、料理を「見る」だけでなく、何かを「体験できる」要素を提示することが、来店の魅力を飛躍的に高めます。
例えば、客が自ら食材を焼くスタイルの店、麺の固さや味の濃さを細かく選べる楽しさ、あるいはその店独自のユニークな注文方法や食べ方のルールなど、「参加型」の要素は視聴者の好奇心を強く刺激します。
さらに、動画の視聴者とのインタラクションを促す工夫も重要です。動画内で特定のハッシュタグの使用を促したり、コメント欄で質問を募集したりすることで、視聴者は動画への参加意識を持ちやすくなります。「自分もこの場所へ行ってみたい」「この体験をSNSで共有したい」という行動意欲を喚起することで、動画は単なる情報伝達ツールに留まらず、来店後のUGC(User Generated Content)生成へと繋がり、さらなる拡散を生む好循環を生み出すでしょう。
5. 分かりやすい情報と親切なナビゲーション
外国人にバズるショート動画は、視覚的な魅力だけでなく、外国人旅行者が来店する上で必要となる実用的な情報が、簡潔かつ分かりやすく提示されていることが不可欠です。具体的には、明確な店名、最寄りの駅や目印となるランドマークなどの場所情報、正確な営業時間、予約の可否、そして特に重要なのが、現金のみか、クレジットカードやQRコード決済などキャッシュレスに対応しているかといった支払い方法の情報です。
これらの情報は、動画のキャプションやコメント欄に多言語で補足したり、Googleマップへの直接リンクを貼ったりすることで、さらに親切なナビゲーションを提供できます。情報へのアクセスが容易であればあるほど、視聴から「実際に行ってみよう」という行動へのハードルが下がり、迷うことなく来店に繋がりやすくなります。動画の魅力を最大化するためにも、情報提供の分かりやすさと利便性を徹底することが、外国人観光客の来店を促進する上で非常に重要なポイントとなります。
ショート動画を実際の来店につなげるには
ショート動画がインバウンド客の来店意欲を刺激することは先に述べた通りですが、単に動画を投稿するだけでは実際の来店には繋がりません。視聴者の興味を具体的な行動へ移すための、シームレスな導線設計が不可欠です。以下に、ショート動画から来店までの効果的な導線設計のポイントを解説します。
1. 動画内での明確なCTA(Call to Action)設定
ショート動画で視聴者の心を掴んだら、次に重要なのは具体的な行動を促す「CTA(Call to Action)」を動画内に明確に設定することです。ただ漠然と「お店に来てね」と伝えるのではなく、「予約はこちらから!」「もっと知りたい方はプロフィールをチェック!」「Googleマップで場所を確認しよう!」といった具体的な指示を、動画の冒頭、中間、そして最後に繰り返し表示しましょう。
視覚的に目立つテキストオーバーレイや、簡潔で分かりやすいナレーションを効果的に使うことで、視聴者は次に何をすべきか迷うことなくスムーズに行動へ移れます。特に、来店へのモチベーションが高まった瞬間にCTAを提示することが重要です。曖昧な表現を避け、「何をすれば、どうなるのか」を明確に提示することで、視聴者の「行ってみたい」という気持ちを具体的な「行動」へと確実に繋げることができます。これは、インバウンド客が言葉の壁を感じることなく、スムーズに次のステップへ進むための不可欠な要素です。
2. プロフィール欄・キャプションの最適化と多言語対応
ショート動画で興味を持った外国人観光客が、次に必ずと言っていいほど訪れるのが、投稿者のプロフィール欄や動画のキャプションです。これらを来店への「情報ハブ」として徹底的に最適化することが、実際の来店に繋げる上で非常に重要です。
まず、店舗の基本情報として、店名、正確な営業時間、定休日、電話番号、最寄りの駅からの分かりやすいアクセス方法を簡潔に記載しましょう。特に、予約を促す場合は、オンライン予約サイトへのURLや、直接予約の可否を明記し、可能であれば多言語対応の予約システムへの導線を設けることが効果的です。さらに、他のSNSアカウント(例:InstagramからYouTubeへ、TikTokからInstagramへなど)へのリンクも設置し、より多様な情報収集を可能にします。
そして最も重要なのは、これらの情報を日本語だけでなく、英語、中国語(簡体字)、韓国語など、主要な訪日客が使用する言語で併記することです。翻訳ツールに頼りきりではなく、自然で分かりやすい表現を心がけることで、外国人観光客はストレスなく必要な情報を得られ、来店へのハードルが大きく下がります。
3. 外部ツールとの連携強化(Googleマップ、予約サイト)
ショート動画から実際の来店へと繋げるには、地図情報や予約システムといった外部ツールとのシームレスな連携が不可欠です。外国人観光客にとって、旅先での位置確認や予約は大きな課題になりがちだからです。
まず、プロフィール欄や動画キャプションにGoogleマップの店舗リンクを必ず貼るようにしましょう。これにより、視聴者はワンクリックで店の正確な位置、現在地からのルート案内、詳細な営業時間、混雑状況などを瞬時に確認できます。これは、特に初めての土地を訪れる外国人にとって、心理的・物理的な来店ハードルを劇的に下げる最も効果的な方法の一つです。
次に、予約システムとの連携です。日本のグルメサイトだけでなく、TableCheckやOpenTableといった多言語対応のオンライン予約サイトへ誘導することで、外国人が言葉の壁を感じることなくスムーズに予約できるようになります。リアルタイムで空席状況を確認し、予約が完了できるシステムは、外国人観光客にとって非常に利便性が高く、来店への強力な後押しとなります。これらの連携を強化することで、視聴者の「行きたい」という気持ちを確実に「行動」へと繋げられるでしょう。
4. UGC(User Generated Content)の促進と活用
実際の来店を強力に後押しし、さらに次の顧客を生み出す上で欠かせないのが、UGC(User Generated Content:ユーザー生成コンテンツ)の促進と戦略的な活用です。現代のインバウンド客は、公式情報だけでなく、他の旅行者が実際に体験し、共有したリアルな声やレビューを非常に重視します。
まず、動画内で店舗独自のハッシュタグを明確に提示し、来店客にそのタグを付けてSNS投稿を促しましょう。「#(店舗名)_Tokyo」や「#(店舗名)_Japan」のように、外国人にも分かりやすく検索しやすいタグを設定するのが効果的です。さらに、「ハッシュタグをつけて投稿してくれた方にはワンドリンクサービス」といった特典を提供することで、UGC投稿へのインセンティブを高めることも有効です。
投稿されたUGCは、公式アカウントで積極的にシェアしたり、ストーリーズ機能で紹介したりすることで、他の潜在顧客にも「この店は本当に人気がある」「自分も行ってみんなにシェアしたい」という好循環を生み出します。このように、来店を促すだけでなく、来店客自身が新たな情報発信者となるような仕組みを構築することが、持続的なインバウンド集客に繋がる重要なポイントとなります。
今日から実践!外国人に響くショート動画の作り方
訪日外国人観光客の心を掴み、実際の来店に繋がるショート動画を作るには、いくつかのポイントを押さえる必要があります。今日から実践できる具体的な手順とコツを解説します。
1. ターゲットとコンセプトの明確化
外国人に響くショート動画を制作する上で、まず根幹となるのは「誰に(ターゲット)」動画を届けたいのか、そして「何を伝えたいのか(コンセプト)」を明確にすることです。ここが曖昧だと、どんなに凝った動画を作っても、狙った層に響かず、メッセージも伝わりにくくなります。
ターゲットの設定では、「訪日外国人」と一括りにせず、より具体的に掘り下げてみましょう。
例えば、欧米からのファミリー層なのか、アジアからの若年層カップルなのか、特定の日本食(ラーメン、寿司、居酒屋料理など)を熱心に探している層なのか。
ターゲットによって、彼らが求める情報や響く表現、好む動画プラットフォームが大きく異なります。
彼らの文化背景やSNS利用習慣をリサーチすることで、よりパーソナライズされたコンテンツ制作が可能になります。
次に、コンセプトです。「伝統的な日本の食文化を体験できる店」「地元の人しか知らない隠れた名店」「日本の最新トレンドグルメを発信する店」など、お店が持つ唯一無二の魅力を言語化しましょう。このコンセプトが動画全体の一貫した軸となり、制作における迷いを減らし、視聴者にもお店の個性や価値が明確に伝わります。
明確なターゲットとコンセプトがあれば、動画の方向性が定まり、効率的かつ効果的なコンテンツ制作に繋がります。
2. 構成とシナリオの作成
ショート動画は、視聴者の興味を一瞬で引きつける「冒頭の数秒」が勝負です。そのため、動画の構成とシナリオを事前にしっかりと練ることが成功の鍵となります。
まず、冒頭のフックには最大限の力を注ぎましょう。最初の1〜3秒で、視聴者に「この動画、面白そう!」と感じさせるインパクトのある映像を挿入します。例えば、湯気がダイナミックに立ち上る料理のクローズアップ、職人の鮮やかで芸術的な手さばき、あるいは息をのむような美しい店内や外観の風景など、視覚的に驚きや感動を与える要素を取り入れましょう。
動画全体では、「見せる」要素を最優先します。長々とした説明は避け、調理の過程で食材が変化していくシズル感、完成した料理の鮮やかな彩り、活気ある店内の様子、そしてスタッフの温かい笑顔など、写真だけでは伝えきれない「ライブ感」を最大限に引き出します。視聴者にその場にいるかのような没入感を提供することで、強い印象を与えられます。
さらに、動画全体で伝えたいメッセージを一つに絞り、シンプルなテキストオーバーレイや短いナレーションで補足しましょう。特に、外国人観光客が来店に際して必要となる店名、場所、営業時間、公式SNSアカウント名などの重要情報は、動画の冒頭や最後に繰り返し表示したり、視覚的に目立つように工夫したりすることで、迷うことなく次の行動に繋げることができます。簡潔かつ効果的な情報提示を心がけましょう。
3. 撮影と編集のポイント
プロ仕様の機材がなくても、最近のスマートフォンは高画質で性能も高いため、魅力的なショート動画を十分に作成できます。大切なのは、いくつかの撮影と編集のコツを押さえることです。
まず、明るさとアングルです。料理が最も美味しく見えるよう、自然光を最大限に活用し、明るい場所で撮影しましょう。様々なアングル(料理を真上から捉える俯瞰、器の質感を強調するローアングル、素材の質感を伝えるクローズアップなど)から撮影することで、動画に奥行きと立体感が生まれ、単調さを避けられます。特に、湯気やソースの光沢、食材の鮮やかな質感などが伝わるよう、細部にまで気を配りましょう。
次に、「シズル音」の活用です。揚げ物が油でジュージューと揚がる音、食材を切るシャープな音、麺を力強くすする音など、食欲をそそるリアルな音を積極的に取り入れましょう。可能であれば外部マイクを使用し、クリアに録音した音声を編集で強調することで、視聴者の聴覚を刺激し、より没入感を高めることができます。
動画の雰囲気に合った著作権フリーのBGMを選定することも重要です。日本の伝統的な和風のBGMや、明るくリズミカルなBGMは、視聴者の気分を高め、動画の魅力を引き立てます。
そして、外国人向けの動画においては、英語のテロップや字幕を入れることを強く推奨します。料理名、店の特徴、注文方法などの重要情報は必ず多言語で記載し、情報へのアクセスを容易にしましょう。
最後に、テンポの良いカット割りです。ショート動画は飽きさせないことが肝心です。視聴者が最後まで楽しめるよう、カットを細かく、スピーディーに切り替えることで、動画全体に心地よいリズム感と躍動感を与えましょう。これらのポイントを実践することで、スマートフォンだけでもプロ並みの魅力的なショート動画が制作可能です。
4. 投稿と導線設計
動画の制作が終わったら、それを単に投稿するだけでなく、視聴者の「行きたい!」という気持ちを実際の来店という行動に繋げるための「導線」をしっかりと設計することが重要です。
まず、適切なプラットフォームの選択です。ターゲット層が最も利用しているSNS(TikTok、Instagramリール、YouTube Shortsなど)を選び、それぞれのプラットフォームの特性やトレンドに合わせた動画フォーマットで投稿することで、より多くの露出が期待できます。
次に、効果的なハッシュタグの活用です。「#JapanFood」「#TokyoEats」「#(具体的な料理名)」「#(お店の正式名称)」「#VisitJapan」など、外国人が実際に検索しそうなキーワードを複数含んだハッシュタグを戦略的に使用しましょう。これにより、動画がより多くのユーザーの目に触れる機会が増えます。
そして、最も重要なのがプロフィールとキャプションの充実です。プロフィール欄には、多言語での店舗情報(正確な住所、営業時間、電話番号、オンライン予約サイトのURLなど)を詳細に記載し、特に外国人観光客にとって必須となるGoogleマップへの直接リンクも忘れずに貼りましょう。動画のキャプションにも、簡潔な店舗紹介と、具体的なCTA(例:「予約はプロフィールのリンクから!」)を盛り込むことで、視聴者が迷わず次のステップへ進めるように促します。
さらに、UGC(User Generated Content:ユーザー生成コンテンツ)の促進も非常に効果的です。来店した外国人客に、店舗専用のハッシュタグ(例:「#(お店の名称)_Japan」)を付けてSNSに投稿してもらうよう積極的に促し、可能であれば「ハッシュタグ投稿でワンドリンクサービス」といった特典を提供することも有効です。来店客が発信するリアルな口コミは、他の潜在的な外国人観光客にとって最も信頼性の高い情報源となり、新たな来店者を呼び込む強力な好循環を生み出すでしょう。
ショート動画でインバウンド集客を成功させたモデルケース
ショート動画は、インバウンド集客において強力なツールとなり得ます。ここでは、東京、大阪、福岡に実在する店舗をモデルに、ショート動画を活用して外国人観光客の集客に成功した具体的なケースを3つご紹介します。
モデルケース1:東京の老舗ラーメン店「A」
東京の下町にひっそりと佇むラーメン店「A」は、創業から半世紀以上の歴史を誇る老舗ですが、デジタルの波に乗り遅れ、SNSでの情報発信に課題を抱えていました。しかし、増え続けるインバウンド客の需要に応えるべく、ショート動画に着目し、その特性を最大限に活かした集客戦略を展開しました。
成功のポイントは、日本の伝統的な「職人技」と「食の感動」をストレートに伝える動画作りでした。 まず、店主が大きな寸胴鍋でスープを丁寧に混ぜる様子、手際よく麺を茹で上げ、湯切りをする迫力ある動作、そして丼に具材を美しく盛り付ける一連の職人芸を、BGMを排し調理のシズル音(湯切り音、包丁の音、スープを注ぐ音など)を際立たせた動画として投稿しました。この「ASMR(Autonomous Sensory Meridian Response)」的なアプローチが、日本の文化や職人技への関心が高い外国人視聴者の間で瞬く間に拡散されました。
さらに、実際に来店した外国人観光客がラーメンを初めて口にする瞬間の驚きと感動に満ちた表情や、思わず漏れる「Oishi!」というリアルな声を短い動画として切り取り、投稿しました。これらの飾らない反応は多くの視聴者の共感を呼び、「自分も同じ体験がしたい」という強い来店動機に繋がりました。
動画を見た視聴者がスムーズに来店できるよう、プロフィール欄にはGoogleマップのリンクを設置し、英語で簡潔なメニュー紹介も加えました。これにより、言語の壁を感じることなく、外国人観光客が店舗情報を得られるよう配慮したのです。
結果として、 動画投稿後、特に欧米圏からの来店が顕著に増加し、店舗前には連日行列ができるようになりました。来店客からは「動画を見て来ました!」という声が多数寄せられ、ショート動画が強力な集客ツールとして機能していることを実感しています。
モデルケース2:大阪の体験型お好み焼き店「B」
大阪の主要観光地近くに位置するお好み焼き店「B」は、外国人観光客に単に食事を提供するだけでなく、「日本の食文化を体験できる場」としての価値を伝えることを目指し、ショート動画を戦略的に活用しました。
彼らの成功の鍵は、「参加する楽しさ」を視覚的に訴えかけることにありました。 まず、外国人客がテーブルに設置された鉄板で、スタッフの親切なアドバイスを受けながら自分でお好み焼きを焼く過程を、コミカルかつ分かりやすい動画で紹介しました。「Do It Yourself (DIY)」という要素は、海外の若年層を中心に「楽しそう」「面白そう」と強く受け入れられ、特にTikTok上で爆発的な人気を博しました。
さらに、「完成までのストーリー」を効果的に見せる工夫も凝らしました。生地を混ぜるところから始まり、具材を鉄板に乗せ、見事にひっくり返し、最後にソースとマヨネーズで自分好みにデコレーションするまでの一連の流れを、数秒のタイムラプスや早送りでテンポ良く見せました。これにより、視聴者は「自分で作った達成感」を疑似体験でき、実際に来店した際の期待感を高めました。
加えて、来店客に対して「#B_Osaka」「#MyOkonomiyaki」といったハッシュタグを付けたSNS投稿を促すキャンペーンを実施。特典としてオリジナルステッカーを進呈することで、UGC(ユーザー生成コンテンツ)の創出を強力に促進しました。
結果として、 体験型の動画はTikTokを中心に広く拡散され、「大阪に行ったらBのお好み焼きを絶対に体験したい!」という声が世界中から多数寄せられるようになりました。オンライン予約システムへのアクセスも飛躍的に増加し、週末を中心に店内は多くのインバウンド客で賑わいを見せ、活気に満ち溢れています。
モデルケース3:福岡の個性派居酒屋「C」
福岡のビジネス街に店を構える居酒屋「C」は、長年地元客に愛されてきた「隠れた名店」でしたが、増加するインバウンド客へのアプローチ方法に試行錯誤していました。そこで彼らが注目したのは、お店の料理だけでなく、「個性的な人(大将)と、日本の居酒屋文化そのもの」を伝えるショート動画でした。
成功のポイントは、人間味あふれる「大将のキャラクター」を前面に押し出したことです。 一見すると無愛想ながらも、その料理の腕は超一流、時折見せる職人ならではの笑顔が魅力的な大将を動画の主役に据えました。大将が豪快に魚を捌く姿や、常連客との軽妙ながらも心温まるやり取りを短い動画として切り取り、「一見近寄りがたいけれど、実は温かい」というギャップを面白おかしく表現しました。この人間性が視聴者の共感を呼び、大きな話題となりました。
また、「日本の居酒屋文化」そのものを体験できる動画も積極的に制作しました。例えば、「とりあえずビール」という最初のオーダーの仕方、隣り合わせた見知らぬ客同士が自然に交流する様子、様々な小皿料理をシェアしながら談笑する光景など、単なるグルメ紹介に留まらない「文化体験」としての居酒屋の魅力を伝えました。これは、一般的な観光客には馴染みが薄い日本のローカルな居酒屋文化への関心を大いに刺激しました。
動画内の日本語の会話には、シンプルな英語のテロップを付けることで、外国人にも内容が直感的に理解できるように配慮しました。複雑な説明は避け、視覚と感情で楽しめるような工夫を凝らしたのです。
結果として、 大将のキャラクター動画がSNSで瞬く間に話題となり、「あの無愛想だけど味のある大将に会いたい!」「本物の日本のローカル居酒屋を体験したい」という明確な目的意識を持った外国人観光客が急増しました。Googleマップのレビュー欄にも、大将の人間性やお店の温かい雰囲気に関するコメントが多数寄せられ、新たな集客の原動力となっています。
外国人観光客を惹きつけるショート動画で飲食店集客を成功させよう
現代において、飲食店のインバウンド集客にショート動画は不可欠です。外国人観光客の多くは、旅行先の情報収集にSNSや動画サイトを積極的に利用しており、視覚的・直感的に訴えかけるショート動画は、言語の壁を越えて「行ってみたい」という強い来店動機を生み出します。
動画制作では、料理のシズル感やライブ感を最大限に引き出すことが重要です。調理の過程や湯気、食材の音など、五感を刺激する映像は視聴者の食欲を掻き立てます。さらに、ターゲットとなる外国人観光客が最も利用するプラットフォームを選び、ただ投稿するだけでなく、プロフィール欄やキャプションに多言語対応のGoogleマップリンクや予約サイトへの導線を明確に設置するなど、来店までのシームレスな流れを設計することが成功の鍵となります。