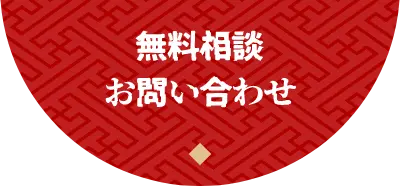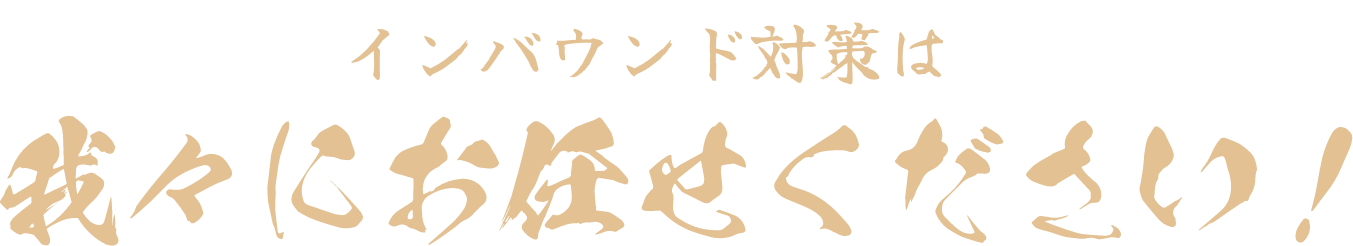京都でインバウンド集客を成功させるには?3つのモデルケースから学ぶ実践的な戦略
【目次】
今、京都の飲食店がインバウンド集客に力を入れるべき理由
外国人観光客が急増する中、京都の飲食店にとってインバウンド集客は喫緊の課題です。本章では、なぜ今こそ集客に注力すべきなのか、市場の現状と京都が持つ独自の強み、そして多様化する顧客のニーズについて解説します。
インバウンド市場の現状と京都が持つ強み
2023年以降、世界の旅行需要は急速に回復し、特に京都は日本を代表する観光地として、多くの外国人観光客で賑わっています。
この回復の勢いはコロナ禍で停滞していた海外旅行の「リベンジ消費」とも称され、待望の日本旅行に多額の費用を投じる人も少なくありません。 したがって、単に客数を増やすだけでなく、客単価の向上も期待できる絶好の機会です。
京都は、単なる観光地ではなく、世界的な文化都市としてのブランド力を確立しています。清水寺や伏見稲荷大社といった歴史的建造物だけでなく、茶道や京料理、和菓子といった食文化も、外国人観光客にとって大きな魅力です。これらの要素が組み合わさることで、欧米、アジア、中東など多様な国や地域から、幅広い層の観光客を引きつけています。政府の観光戦略とも相まって、インバウンド観光客の数は今後も増加が予測されており、この流れに乗ることは飲食店の経営において不可欠です。
ターゲット層の多様化とそれに合わせた集客の重要性
現代の外国人観光客は、パッケージツアーで有名な観光地を巡るだけの旅から、自分だけの特別な体験を求める「コト消費」へとシフトしています。彼らは、ガイドブックに載っていないような、よりローカルで本格的な日本の文化や日常に触れることを強く望んでいます。
そのため、彼らは高級な日本料理店に留まらず、地元の人が通う居酒屋、本場の味を堪能できるラーメン店、独自の雰囲気を楽しむカフェなど、様々なジャンルの飲食店に足を運ぶようになりました。さらに、食に対する価値観も多様化しており、例えばヴィーガン(菜食主義)やハラル(イスラム教徒向け)に対応したメニューを求める声は年々増加傾向にあります。
このような多様なニーズに応えるためには、画一的なサービスでは十分ではありません。店舗のコンセプトや強みを再認識し、「私たちはどの国の、どのような興味を持つ層に、どのような体験を提供したいのか」という問いを明確にすることが、インバウンド集客成功の第一歩となります。このターゲティングが曖昧なままでは、効果的な集客施策を打つことは難しいでしょう。
【モデルケース1】伝統とモダンを融合させた「町家カフェA」
京都市の中心部にある築100年以上の町家を改装したカフェ。インバウンド集客に成功した背景には、日本の伝統的な建築美を活かしたブランディングと、現代のニーズに合わせたサービス提供がありました。
成功の鍵: 伝統的な雰囲気を活かしたブランディング
町家カフェAは、建物の持つ歴史的価値そのものを最大の武器としました。 外国人観光客は、京都ならではの伝統的な空間で食事をすることを強く望んでおり、店内は日本の古き良き文化を感じさせるデザインで統一。また、カフェのロゴやメニュー表、使用する食器に至るまで、和の要素を取り入れた統一感のあるデザインでブランディングを徹底。これにより、「本物の京都体験」ができる場所として、口コミで評判が広まりました。
多言語対応:多言語メニューやSNS発信の工夫
英語、中国語(簡体字・繁体字)、韓国語のメニューを作成し、外国人観光客が安心して注文できるよう配慮しました。また、メニューには料理の写真だけでなく、食材の産地や料理の背景にあるストーリーを簡単な説明文とともに記載。さらに、InstagramやFacebookでは、各国の言語で「抹茶ラテの作り方」や「京野菜を使った旬のスイーツ」など、興味を引くコンテンツを定期的に発信し、来店前から期待感を高める工夫をしました。
決済手段:キャッシュレス決済の導入で利便性を向上
外国人観光客の多くは、自国で普及しているキャッシュレス決済を日本でも利用したいと考えています。町家カフェAでは、クレジットカードはもちろんのこと、AlipayやWeChat Payといったモバイル決済、さらには主要なQRコード決済にも対応しました。これにより、現金を持ち歩かない旅行者でも気軽に利用でき、機会損失を防ぐことに成功。レジ前の混乱も解消され、スムーズな顧客対応が可能になりました。
【モデルケース2】体験型サービスで差別化を図った「日本料理店B」
京都市の料亭街にある高級日本料理店。一般的な高級店との差別化を図るため、食事だけでなく、日本の文化を「体験」として提供する戦略を取り入れました。高価格帯をターゲットにしつつ、単なる食事を超えた「特別な思い出作り」の場として認知されることに成功しました。
成功の鍵:料理教室や着物体験など、独自の体験コンテンツを提供
日本料理店Bは、「料理を食べる」だけでなく「日本料理を学ぶ」という体験を提供。例えば、季節の食材を使った簡単な京料理の作り方を教える料理教室や、着付け師による着物体験と組み合わせたプランを用意しました。これにより、顧客は単なる食事以上の深い満足感を得ることができ、SNSでも発信したくなるようなユニークなコンテンツが生まれました。
口コミ戦略: SNS映えを意識したメニューとフォトスポット
体験型サービスをSNS戦略と連動。芸術品のように美しい盛り付けの懐石料理や、庭園を望む個室など、写真や動画を撮りたくなる要素を随所に配置しました。さらに、着物姿で記念撮影ができる専用のフォトスポットを設けることで、顧客が自発的に魅力を発信してくれるUGCを創出しました。
予約システム: 外国人観光客向けのオンライン予約システムの導入
多くの外国人観光客は、言語の壁や時差の問題から、電話での予約をためらいがちです。そこで、多言語対応(英語、中国語など)のオンライン予約システムを導入しました。これにより、海外からでもスムーズに予約が完了できるようになり、予約受付の手間が減っただけでなく、事前決済を可能にすることで無断キャンセルを大幅に削減することにも成功しました。
【モデルケース3】SNSとUGCを活用した「ラーメン店C」
京都駅近くにある、若者や個人旅行者に人気のラーメン店。古くからの伝統的なラーメンとは一線を画し、現代的なSNSを活用したマーケティングでインバウンド集客を成功させました。特に、「本場の日本のラーメン」を求めて来店する外国人観光客の心をつかむことに成功しています。
成功の鍵:ターゲットに合わせたSNSアカウント運用とインフルエンサー活用
ラーメン店Cは、InstagramやTikTokといった写真・動画がメインのSNSに特化。英語と日本語で、美味しそうな湯気や麺の食感を伝える動画、スープのこだわりを伝える写真などを投稿しました。さらに、フォロワー数の多いインフルエンサーを招いて試食会を開催し、その様子を投稿してもらうことで、彼らのファン層にもリーチすることに成功しました。これにより、短期間で認知度を飛躍的に向上させました。
UGC(ユーザー生成コンテンツ): 投稿を促すためのキャンペーンやハッシュタグ戦略
顧客が自ら発信する「UGC(ユーザー生成コンテンツ)」を増やす戦略を徹底しました。具体的には、ラーメンを注文した際に、店員が「写真を撮ってInstagramに投稿すると、特製の味玉をサービスします」と英語で声をかけました。これにより、多くの投稿が生まれ、#kyotoramenCといった専用ハッシュタグで、リアルな口コミが広がりました。
マップサービス:Google マップやトリップアドバイザーでの情報発信強化
SNSでの拡散に加え、来店を検討している外国人観光客が必ずチェックするGoogle マップとトリップアドバイザーの情報も最適化しました。店舗の営業時間、正確な位置情報、多言語対応のメニュー写真を常に最新の状態に保ちました。また、寄せられたレビューには多言語で丁寧に返信し、顧客との信頼関係を築くことに努めました。この丁寧な対応が、さらに高評価につながり、集客の好循環を生み出しました。
モデルケースに学ぶ!明日から始められるインバウンド集客4ステップ
本記事で紹介した成功事例から、インバウンド集客を始めるための具体的な4つのステップが見えてきます。規模の大小に関わらず、明日からでも実践できる内容ですので、ぜひ自店の集客戦略に取り入れてみましょう。
ステップ1:ターゲットと自店の強みを明確にする
インバウンド集客を成功させる上で、最も重要なのは「誰に、何を届けたいか」という明確なターゲティングです。闇雲に外国人全体をターゲットにするのではなく、特定の層に焦点を絞ることで、より効果的かつ効率的な集客戦略を立てることができます。
例えば、若者向けのラーメン店であれば、日本のポップカルチャーやアニメに興味を持つ層、SNSでの情報発信を好む層がターゲットになります。
一方で、高級な京料理店であれば、富裕層や食文化に深い関心を持つ層をターゲットとすべきです。
ターゲット像が明確になることで、その層が利用するプラットフォームや、響く情報、適切な価格設定など、具体的な施策が導き出せます。
次に、自店の強み(提供する料理、店の雰囲気、立地など)を客観的に再認識しましょう。ラーメン店Cであれば「SNS映えするメニュー」、町家カフェAであれば「歴史的な建物の雰囲気」が強みです。これらの強みをターゲットのニーズと結びつけ、「自店の強みが、ターゲットのどのような期待に応えられるのか」を言語化することが、インバウンド集客の成功の第一歩となります。
ステップ2:多言語対応とキャッシュレス決済の環境を整備する
集客施策を打つ前に、外国人観光客が安心して利用できる基本的な「受け入れ体制」を整えることが不可欠です。これは、店員と顧客のコミュニケーションの円滑化、そして決済の利便性向上に直結し、顧客満足度を大きく左右します。
まず、多言語対応についてです。最低限、英語のメニューを作成するのはもちろん、料理のイメージが伝わりやすい写真や、アレルギー情報をアイコンで表示するなど、視覚的な工夫も重要です。 主要な言語(中国語、韓国語)のメニューも用意できれば、さらに安心感を与えられます。また、全てのスタッフが流暢な外国語を話す必要はありません。指差しで使える簡単な会話集や、翻訳アプリの活用を推奨し、笑顔で丁寧なジェスチャーを心がけるだけでも、顧客は「歓迎されている」と感じてくれます。
次に、キャッシュレス決済の導入です。外国人観光客の多くは、自国で普及しているクレジットカードやモバイル決済を日本でも利用したいと考えています。Visa、Mastercard、JCBといった国際ブランドはもちろん、AlipayやWeChat Payといったモバイル決済、さらにPayPayなどの主要なQRコード決済にも対応することで、現金を持ち歩かない旅行者でも気軽に利用でき、機会損失を大幅に防ぐことができます。
さらに、無料Wi-Fiの提供も、基本的なインフラとして重要です。多くの観光客は、スマートフォンの地図アプリや翻訳アプリを利用するためにWi-Fiを必要とします。店舗で無料Wi-Fiを提供することで、彼らが情報収集しやすくなるだけでなく、SNSへの投稿を促すことにもつながります。
ステップ3:SNS・オンラインプラットフォームでの情報発信を強化する
ターゲットに合わせたプラットフォームを選び、戦略的に情報発信を行うことで、潜在顧客との接点を増やし、来店を促すことができます。
1. SNSの使い分けと戦略的なコンテンツ発信
ターゲット層に合わせて、効果的なSNSを使い分けましょう。
- Instagram
料理の見た目や店の雰囲気を重視する層に最適です。高品質な料理写真や、食事のシズル感を伝えるリール動画は、視覚的に訴求力が高く、海外のフォロワーを獲得しやすい傾向にあります。 - TikTok
若者層や、よりエンターテインメント性を求める層に響きます。スタッフの個性や、料理ができるまでのプロセスを短尺動画で紹介するなど、親近感を持たせるコンテンツが効果的です。 - Facebook / X(旧Twitter)
イベント情報や最新の営業情報など、テキストベースでの情報発信に向いています。
2. Google マップとトリップアドバイザーの最適化
多くの外国人観光客は、お店を探す際にGoogle マップやトリップアドバイザーを利用します。これらのプラットフォームでの情報発信は、集客に直結する重要な要素です。
- Google マップのビジネスプロフィール
営業時間、メニュー、多言語対応の有無、写真などを常に最新の状態に保ちましょう。特にメニュー写真の多言語表記は、来店前の不安を解消する上で非常に重要です。 - レビューへの丁寧な返信
寄せられたレビューには、感謝の気持ちを伝える返信を必ず行いましょう。ポジティブなレビューにはもちろん、ネガティブなレビューにも真摯に対応することで、店の信頼性が高まります。
3. インフルエンサーマーケティングの活用
インフルエンサーと協力することで、短期間で店の魅力を多くの人々に広めることができます。
- マイクロインフルエンサー
フォロワー数は多くなくても、特定の分野に特化した熱心なファンを持つ「マイクロインフルエンサー」とのコラボレーションは、高いエンゲージメントが期待できます。 - 依頼時のポイント
お店の世界観やターゲット層と合うインフルエンサーを選びましょう。また、報酬形態(食事招待、現金など)を明確にすることで、トラブルを防ぎ、より良い関係を築くことができます。
ステップ4:口コミとレビューを分析し、サービスを改善する
外国人観光客にとって、Google マップやトリップアドバイザーなどの口コミサイトは、お店選びの最も重要な情報源の一つです。これらのレビューを単なる評価として見るのではなく、顧客からの貴重なフィードバックとして捉え、積極的に活用することが成功の鍵となります。
1. 口コミへの丁寧な返信
寄せられたレビューには、良い評価、悪い評価に関わらず、必ず多言語(英語は必須)で丁寧に返信しましょう。
- ポジティブなレビューへの返信
感謝の気持ちを伝えるだけでなく、「〇〇様にお会いできて光栄でした」「次回は〇〇をお試しください」といったパーソナライズされたメッセージを添えることで、顧客は「自分は大切にされている」と感じ、リピーターになる可能性が高まります。 - ネガティブなレビューへの返信
批判的な意見にも、感情的にならず、真摯に対応することが重要です。「ご期待に沿えず申し訳ございません。〇〇の件につきましては、今後のサービス改善に活かしてまいります」など、具体的な改善策を提示することで、他の潜在顧客にも誠実な姿勢が伝わり、信頼性を維持できます。
口コミ管理についてはこちらの記事でも詳しく紹介しています。ぜひ併せてご覧ください。
【多言語対応】口コミ返信テンプレ公開—★4.5を維持する訪日客集客口コミ術
2. 口コミ分析の重要性
口コミは、自店の強みと弱みを客観的に把握できる宝庫です。
- 強みの発見
「スタッフの笑顔が素敵」「ラーメンのスープが最高」といったポジティブな意見は、自店のセールスポイントを再確認する貴重なデータとなります。 - 改善点の発見
「注文方法が分かりにくかった」「Wi-Fiが繋がりにくい」といったネガティブな意見は、サービス改善の具体的なヒントとなります。 これらの分析を習慣化し、PDCAサイクル(計画→実行→評価→改善)を回すことで、サービスの質を継続的に向上させることができます。
インバウンド集客は「おもてなし」から始まる
インバウンド集客の最終目的は、単発の売上を上げることではありません。最も重要なのは、「また来たい」と思わせるような、心に残る顧客体験を提供することです。
これは、日本の文化である「おもてなし」の精神に通じます。単に商品を売るだけでなく、お客様一人ひとりに寄り添い、丁寧で温かいサービスを提供して、特別な思い出を演出しましょう。
感動的な体験をした顧客は、帰国後もSNSや口コミサイトで積極的に情報を発信してくれます。これにより、新たな顧客を呼び込むだけでなく、リピーターとして再訪してくれる可能性も高まります。リピーターは、お店の売上を安定させるだけでなく、熱心なファンとしてお店の魅力を広める「アンバサダー」のような存在となるのです。
インバウンド集客は、目先の利益を追うだけでなく、長期的な視点で「おもてなし」の心を持って取り組むことが成功の鍵です。顧客との信頼関係を築き、良い循環を生み出すことで、お店の未来はさらに広がっていくでしょう。